スタジオライフ「バタフライはフリー」観劇 [┣Studio Life]
The Other Life Vol.11
「バタフライはフリー」
作:レオナルド・ガーシュ
訳:黒田絵美子
演出:倉田淳
美術・照明・舞台監督:倉本徹
音響:竹下亮(OFFICE my on)
ヘアメイク:MUU
ヘア協力:葛城奈菜海
衣裳:石飛幸治
演出助手・照明操作:中作詩穂
音響操作:鈴木宏明
版権コーディネート:シアターライツ
企画制作:Studio Life
6月頃に上演する予定だったが、新型コロナの影響で劇団の上演計画を見直し、7月に朗読「言葉の奥ゆき」を上演し、本公演は9月まで延期した。感染対策を万全にして、MAX130席のウエストエンドスタジオで、舞台スペースから2メートルの距離をとったうえで、1席おきの着席…チケット代を上げるでもなく…大丈夫か![]()
入口で手指消毒、靴裏消毒、マスクシールドorフェイスシールドプレゼント。そして、客席への階段は、行きと帰りがかぶらないように、間に暗幕で仕切っている。これは、開演後に到着した客の誘導にも効果的かも。(遅れて登場すると、出演者のごとく目立つので。)開演するまでは、客席にデカい送風機を設置、劇場上部の通風孔もオープン。通常30分前の入場を1時間前に設定して、入場が密にならないように配慮し、公演後は、規制退場を実施している。
「言葉の奥ゆき」の時は、あまりにも早く入場させたことで、逆に客席内での観客同士のトーク止まらない現象が起きていたが、それを防ぐ目的か、早めに入場した客を対象に、フェイスシールドに身を固めた代表による開演前トークが実施された。
私の知る限り、一番すごい対策をしているし、させている。
The Other Life公演は、海外の優れた戯曲を日本に紹介するというテーマで、本公演とは別に上演しているもので、過去に以下のような作品が上演されている。
「Happy Families」(Vol.1、4→本公演)
「THREE MEN IN A BOAT+ワン」(Vol.2、5、8→本公演)
「桜の園」(Vol.3)
「Daisy Pulls It Off」(Vol.6→本公演)
「孤児のミューズたち」(Vol.7)
「BLOOD RELATIONS~血の繋がり~」(Vol.9)
「VANITIES」(Vol.10)
(今回がVol.11なのに、過去7作しかないのは、再演でもVol.ナンバーをプラスしていた過去があったためで、現在は、The Other…で上演後の再演は本公演としているようだ。)
今回の作品は、21歳の青年と19歳の娘がアパートの隣室になって恋に落ちて…という展開なんだけど、その青年が全盲だったことから、母親が出てきたり、娘が出演する芝居の演出家が出てきたり…と、紆余曲折してしまう物語。どうなることかと思わせてからのハッピーエンドで、嬉しいやらホッとするやら、なかなか後味のよい作品でした![]()
では、出演者感想です。
宮崎卓真(ドン・ベイカー)…歌手を夢見る盲目の青年をもはや、準劇団員の宮崎卓真が演じた。歌唱シーンも手に汗握らないし、21歳の青年にしか見えないし、(去年の秋は、10代の息子が2人居るお父さんだったのに…![]() )自分のテリトリーが守られている時の自信に満ちた表情と、それが崩された時の痛々しさのギャップがたまらない
)自分のテリトリーが守られている時の自信に満ちた表情と、それが崩された時の痛々しさのギャップがたまらない![]() 実に庇護欲をそそる存在でした
実に庇護欲をそそる存在でした![]()
生まれつき目が見えないため、過保護な母親に大事に育てられてきたものの、それじゃいけない![]() と奮起して一人暮らしを始めるたドン。隣室のジルとさっそく恋仲になったものの、母親にしてみれば、目のせいで失恋したら…と、それもまた気になるところ。
と奮起して一人暮らしを始めるたドン。隣室のジルとさっそく恋仲になったものの、母親にしてみれば、目のせいで失恋したら…と、それもまた気になるところ。
しっかりしているようで、実は、ものすごくナイーブなドンだから、彼の恋の行方が、とても気になる![]()
ハッピーエンドでよかったね![]()
彼が盲目である、という設定に、ジルと同時に気づいた。それほど自然な演技だったところもすごい![]()
伊藤清之(ジル・ターナー)…ドンの隣室に越してきた19歳の女優志望の女性。ティーンエイジャーだけど、離婚歴あり。初対面の相手に対しても臆することなく、背中のジッパーをあげてほしいとか言えちゃう。会ったその日でも、気持ちが通じれば、ベッドインあり。でも、自分は人を愛せないのではないか、という疑問も感じている。蓮っ葉なようでいて、実は、ドンの母、ミセス・ベイカーの意見を尊重して、愛想尽かしと取られるような行動を取ってみたりする。
揺れる娘心を丁寧に紡いでいて、劇団ヒロインとしての階段をまたひとつ上ったかな![]()
けっこう露出度の高い衣装だったが、思いのほか、逞しい二の腕、てか、肩![]() に、うーん…
に、うーん…![]() となる。マツシンも筋肉質だけど、ここまでの違和感はなかったような…
となる。マツシンも筋肉質だけど、ここまでの違和感はなかったような…
曽世海司(ミセス・ベイカー)…口うるさい母親に見えて、実は、ものすごく愛情深くて、自分からジルに愛想尽かしを頼んだくせに、実際に息子より、変なおじさんを選んだかのようなジルの態度には、めちゃくちゃ腹を立てる。息子からは疎まれているのに、とにかく息子ファースト。その見返りを求めない大きな愛(なんだけど、心は狭い)をコミカルに逞しく表現してくれる。
曽世らしいおしゃべりテイストが役作りにも自然に表れていて、若い恋人たちへのよいスパイスになっていた。
あと、ミセス・ベイカーは児童向けの作家なんだけど、彼女がどんな思いで、ドニーという名の盲目の少年を活躍させたのか、というストーリーには胸が熱くなった。それが途中からドンへのプレッシャーになる、というのも切ないけど、その「愛」にようやく気づいたドンは、もう、大丈夫だよね…![]() と思った。
と思った。
大村浩司(ラルフ・オースティン)…ジルが受けると言っていたオーディション作品のプロデューサー。ジルをすっかり気に入って出演させることにしたらしいが、下心がミエミエ![]() ジルは、彼の誘いに乗って、彼の家に引っ越すと言い出すが…
ジルは、彼の誘いに乗って、彼の家に引っ越すと言い出すが…
芸術家なのか、ヤバイ人なのか、紙一重な感じ。
ドンへの接し方も、ジルからどう思われるか、という部分だけでやっている辺り、「そういうとこだよ」って雰囲気がよかった。他の三人が、すごく繊細な芝居を紡いでいるところに、ガーッと土足で踏み込んで、根こそぎ壊していく感じ。そういう部分を求められていたと思うので、まさに適役だったと思う。
緻密な演出も楽しかったが、訳が若干古いのか、“ホモ”“レズ”という言葉が悪意なく使われていたのには、ちょっと驚いた。さすがに、今は、この呼び方、まずいと思うよ![]()




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
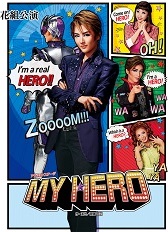


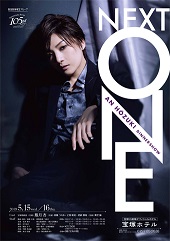




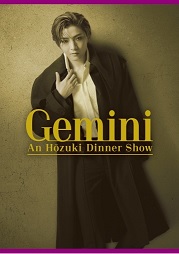
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)


