宝塚雪組東京公演「ONCE UPON A TIME IN AMERICA」観劇 [┣宝塚観劇]
ミュージカル
「ONCE UPON A TIME IN AMERICA」
原作:ハリー・グレイ
脚本・演出:小池修一郎
作曲・編曲:太田健、青木朝子
音楽指揮:西野淳
振付:御織ゆみ乃、若央りさ、桜木涼介、KAORIalive
擬闘:栗原直樹
装置:大橋泰弘
衣装:有村淳
照明:笠原俊幸
音響:大坪正仁
小道具:増田恭兵
映像:奥秀太郎
歌唱指導:やまぐちあきこ、堂ノ脇恭子
演出補:田渕大輔
演出助手:竹田悠一郎
装置補:稲生英介
舞台進行:安達祥恵
もともとの観劇予定日がダメになってしまったため、公演再開が決定したと同時にチケットを探し、どうにか手に入れることが出来た。
観劇は、私の日常、特に宝塚は、会社よりも平常心の保てる場、のはずだった。
日常すぎて、何度も観すぎて、時々居眠りするくらいに。
マスク+眼鏡+オペラグラスという異常な体勢で、花粉症のせいで咳やくしゃみが止まらない状態を「気合い」だけで止め、3時間、石のように舞台を見守った。もしかしたら、望海さんのサヨナラ公演だって、こんなには集中しないかもしれない。(その前にチケットを取れる気がしませんが…![]() )
)
この作品の観劇自体が初めてだったので、(ムラに行っておけばよかったです…![]()
![]()
![]() )どこで歌が入るのかも知らず、トップコンビの静かな会話シーンでは、「ここでもし咳が出てしまったら…」という緊張で、「早く、歌にならないかな…」などと不謹慎なことを考える始末ではありましたが。
)どこで歌が入るのかも知らず、トップコンビの静かな会話シーンでは、「ここでもし咳が出てしまったら…」という緊張で、「早く、歌にならないかな…」などと不謹慎なことを考える始末ではありましたが。
映画も全く知らないので、作品自体が初見だったが、久しぶりに、やりたい放題の小池修一郎を見た![]() 大劇場デビュー作品から小池先生を観ている(厳密に言うと初演の『天使の微笑・悪魔の涙』は観ていなくて、後に全ツを観ました
大劇場デビュー作品から小池先生を観ている(厳密に言うと初演の『天使の微笑・悪魔の涙』は観ていなくて、後に全ツを観ました![]() )私としては、初期の小池作品を思い出すような…そんな感じ。
)私としては、初期の小池作品を思い出すような…そんな感じ。
もちろん、1990年代初めの小池先生は、今みたいな巨匠ではなく新人演出家だったので、お金のかけ方は全然違うのですが、小池先生にとっての、「男の夢」ってこれなんだよね。変わってないな~![]()
脚本家としての小池先生のベースは、「ヴァレンチノ」と「華麗なるギャツビー」にある。バウホールデビューの時、この二作品を考え、結局「ヴァレンチノ」でデビューしたが、大劇場デビュー後3作目に「華麗なるギャツビー」を上演している。つまり、先生の原点って「…ギャツビー」なんだよね、おそらく。
そういう目で本作を観ると、若くてお金のなかった時代に手が届かなかった美しい女性を手に入れるために、滑稽な努力を続ける男、でもその夢は叶わないーという物語に、彼はキュンとなるんだな~と、その共通点にニマニマする。
とはいえ、小池先生がそんな夢を託せるトップスターに、ある程度大人の…というか、ぶっちゃけ中年の男を演じることができる男役は、そうそう現れない。それは、宝塚においては、学年でもなく、実年齢でもなく…雰囲気だから。たとえば、「…ギャツビー」上演時の杜けあきは、研13。今、研13といえば、珠城りょうなんだけど、私は珠城でやさぐれの美学を観たいとは思わない。
そして、やさぐれの美学ができるトップスターといえば、やはり、望海風斗ではないか![]() …と。小池先生、この時を待っていたんだね
…と。小池先生、この時を待っていたんだね![]()
映画を原作としたオリジナル・ミュージカルという点では、「カサブランカ」を思い出すが、「カサブランカ」が白黒映画の雰囲気を出していたのに対して、「ONCE…」はカラー映画だなぁ~と随所に感じる。とはいえ、1幕ラストの楽曲は、作・編曲が太田先生なこともあって、笑うほど似た仕上がりになっていて、ニヤついてしまった。
でも、出てくる雰囲気が、恐ろしいくらい違っていて、第一部のやるせないラストを彩るリックのSolitudeと、ヌードルスのLonelinessが対照的だった。
登場人物がめちゃくちゃ多いのも、小池先生1本物の特長で、特に男役は役柄が多く、しかも同時に登場するので、目がいくつあっても足りない。なんか、すごい作品を観た…![]() という感じだが、それは、約10日間の理不尽な休演期間を経て、ようやく再開した劇場の熱気、一体感を含んだ感想なのかもしれない。
という感じだが、それは、約10日間の理不尽な休演期間を経て、ようやく再開した劇場の熱気、一体感を含んだ感想なのかもしれない。
10年経っても、この劇場の、この空気を忘れることはないだろう、そんな風に思った。会話のシーンではしわぶきひとつ聞こえない。(まあ、咳をしたらすぐに係のおねえさんに声をかけられる…と注意事項に書いてあったけど。)歌が終わると、一曲ごとにショーストップしそうな大拍手。全国ツアーでも、ここまでの大歓迎ぶりは、あまり聞かない。
宝塚ファンの人達の、「待ってました![]() 」という想いが、同じ劇場の中で共有され、2千人の熱気含めて、私の感動を醸成した可能性も否めない。なので、本作についての評価は、平常時ではなかったということで、保留しておきたい。もちろん、すごく感動したし、すごく幸せだったけれども。
」という想いが、同じ劇場の中で共有され、2千人の熱気含めて、私の感動を醸成した可能性も否めない。なので、本作についての評価は、平常時ではなかったということで、保留しておきたい。もちろん、すごく感動したし、すごく幸せだったけれども。
ということで、感想です。
物語は、1920年代から徐々に進んでいく物語軸と、1958年を現在とする終着軸の二本の時間軸を持っている。原作映画は、ヌードルスの記憶の赴くままに、色々な時間軸を行ったり来たりしているらしいが、基本的に、舞台では、1958年から始まって、回想でほぼ時系列に物語を進めて(途中ちょっとだけ1958年を挟む)、主だった物語をすべて見せてから、冒頭の場面に戻り、続きの世界を見せる…という、ある意味典型的な宝塚のミュージカルになっている。
登場人物は、時間軸を飛び越え、若々しい時代と、壮年以降を演じているのだが、奏乃はると演じるファット・モー(ヒロイン・デボラの兄)だけは、若い時代を橘幸が演じているので、時折1958年のシーンがあっても、違いを理解することが出来た。それでいて、同じ人物だとわかるのは、ファット・モーというニックネームが示す通り、彼が太っていて、たぶんあの人はあの人ね、と分かりやすいから。この辺りの作劇テクニックは、小池先生の手練れだな、と感じた。
ローワー・イーストサイド(マンハッタン島のイースト・リバーに突き出した辺り)は、ユダヤ人移民が多く居住している地域で、貧しいながらも夢を持つ若者たちがたくさんいる。デボラ(真彩希帆)は、バレエに精を出し、いつか、世界の皇后になりたいと夢を語る。ヌードルス(望海風斗)は、それなら僕は皇帝になろうと語る。
ヌードルスは、コックアイ(真那春人)、パッツィー(縣千)、ドミニク(彩海せら)ら悪ガキ仲間と、スリやかっぱらいをして生活の糧としていた。ある日、懐中時計を盗むのに失敗した彼らを救ってくれた少年がいた。マックス(彩風咲奈)と名乗るその度胸ある少年と、ヌードルスは意気投合した。
禁酒法の時代、ヌードルスたちは、スピークイージー(もぐり酒場)に密造酒を運ぶ仕事を始める。デボラは、ブロードウェイのオーディションに合格し、夢の一歩を歩き始めた。しかし、ヌードルスは、仲間のドミニクが殺されて怒りが爆発し、相手のバグジー(諏訪さき)と警官(天月翼)を刺してしまい、少年鑑別所に送られてしまう。ちょっとしたWSS![]()
7年の服役後、出所したヌードルスを迎えたのは、マックス、コックアイ、パッツィー。マックスに連れられて、ヌードルスは、ブロードウェイのスターになったデボラのステージを鑑賞する。そして、マックスの経営するスピークイージー“インフェルノ”で、ヌードルスは、デボラと7年ぶりに言葉を交わす。
マックスは、スピークイージーの経営と酒の密輸で、暗黒街のちょっとした顔になっていた。店の看板ショーガール、キャロル(朝美絢)という恋人もいるが、彼の渇きは癒えることがなかった。マックスは、この4人で「アポカリプス(黙示録)の四騎士」になろうと、ヌードルスを誘う。
「アポカリプスの四騎士」は、ジューン・マシスの脚本で、この作品でルドルフ・ヴァレンチノが見出された。その名前を出すところが、小池先生だな~![]() (原作にもあったら、ごめんなさい
(原作にもあったら、ごめんなさい![]() )
)
アポカリプスの四騎士となって以降は、スピークイージーの運営と、酒の密輸以外にも、デトロイトの宝石店を襲ったりして、マックスは悪事のやりたい放題。キャロルは、マックスの悪事を知りつつも、それが自分の愛した男だから…と複雑な心境を吐露、でも、愛がすべて、そこは思考停止して彼と付き合っている。
アポカリプスの新たな仕事は、先方から飛び込んできた。全米運送者組合のジミー(彩凪翔)という男がストライキへの協力を要請してきた。経営者側はイタリアン・マフィアを雇って、ストライキの切り崩しを目論んでいる。裏社会同士の対決にもなる争議は、アポカリプスの勝利に終わる。こうして、アポカリプスは、帳簿に出ない資金源(組合の預り金)を手にすることになる。
ヌードルスは、今やブロードウェイのスターとなり、ハリウッドから誘いを受けるようになったデボラを誘って、ロングアイランドのレストランに出掛ける。この日のためにレストランを貸切にし、スイートルームは真っ赤な薔薇で埋め尽くした。
デボラの返答はNO。ヌードルスは、失恋の痛みを爆発させ、一人激しく歌う。
アポカリプスの面々がハバナで遊び惚けていた時、禁酒法撤廃のニュースが飛び込んでくる。
一方、デボラは、彼女を見出したハリウッドのプロデューサー、サム(煌羽レオ)に新たな愛人、ベティ(星南のぞみ)ができたことで、微妙な立場に置かれてしまう。打ちひしがれるデボラの側には、ローワー・イーストサイド時代から彼女を応援し、共に実績を積んできたニック(綾凰華)の姿があったが、恋愛という意味では、彼女は孤独だった。
インフェルノは最後の荒稼ぎをしていたが、その裏側で、ヌードルスはこれまで貯めてきた資金を元手に不動産投資を提案する。ヌードルスにとって悪事とは、貧困家庭の出身で刑務所出の自分には、ほかに道がなかったから仕方なく手を染めてきたものであって、いつか、デボラに釣り合う真っ当な男になることが、彼の望みだった。しかし、マックスはあくまでも悪事に拘り、子供の時からの夢であった連邦準備銀行襲撃計画をぶち上げる。
悪い男でも好きだと歌っていたキャロルも、こればっかりは、絶対にやらせたくないと、ヌードルスに懇願、警察に密告して、事件を未遂に終わらせてほしいと言う。友達を売ることに躊躇するヌードルスだったが、死なせたくない一心で、密告電話を架ける。一方、ヌードルスの態度を不審に思い、本気じゃない奴は連れて行かない、とマックスはヌードルスを気絶させて、襲撃に出掛ける。
NY市警は、直接逮捕に向かうのではなく、対立組織のフランキー(桜路薫)に情報を横流しし、組織同士の相打ちを狙った。そして、銀行の爆破により、アポカリプスの3人は、全員が死亡した。ヌードルスはファット・モーの助けで阿片窟に隠れたが、阿片のせいか、ひどい幻覚を見る。
ジミーのもとへ、火傷を負ったマックスが現れる。身元不明の死体がマックスのものだと言われたが、実は死んでいなかった。ジミーは、組合の身寄りのない最近の死者の身分証明をマックスに与える。
すべてから逃れて隠遁しようとしたヌードルスが、プールしてあったはずの共有財産を預けた駅のロッカーに行くと、ボストンバッグの中身は空だった。
デボラは、出演したハリウッド映画で賞を取るが、サムのもとを離れる決意を固めていた。
25年後、政府の要人、ベイリー長官の誕生パーティーの招待状を受け取った壮年のヌードルス。キャロルがサナトリウムで療養していることを聞き、そこに向かう。そして、すべての記憶を失くしたキャロルと、ベイリー財団の理事になっていたデボラに再会する。このサナトリウムはベイリー財団のものだったのだ。
ヌードルスは、デボラがベイリーの愛人になっていたことに気づき、ベイリーが誰かということにも気づく。デボラに憧れていたのは、ヌードルスだけではなかったから。
誕生パーティーの控室では、ジミーがベイリーことマックスに最後通告をしていた。彼の汚職への追及の手が伸びており、組合との関係が表沙汰になる前に、自殺してくれ…と。マックスは、人生の幕引き役として、ヌードルスへ自分を殺してくれるように頼む。それがパーティーへの招待の理由だった。
しかし、ヌードルスはそれを断り、去って行く。マックスが自ら拳銃の引き金を引こうとする頃、ヌードルスは、何も叶わなかった人生を思い、歌い続けていた。
めっちゃ、小池先生だな~![]() と思った。それを豪華1本立てにしちゃうところを含めて。
と思った。それを豪華1本立てにしちゃうところを含めて。
私が、めっちゃ柴田先生だと思っている「珈琲カルナバル」と同じくらい痛い男のロマン![]()
ロマンをちゃんと理解して、三次元化してあげている望海風斗、やさしすぎるわ![]()
抜群の歌唱力で、ヌードルスの苦しみを歌い上げるところにもグッとくるが、1958年の方の、みんながタキシードで決めている中、場違いなツイードのジャケットで登場する、しおれたオッサンな感じが、もうたまらなくツボ![]() もうね、こういう姿でも観客の心を打つというのが本物のトップスターなわけよっ
もうね、こういう姿でも観客の心を打つというのが本物のトップスターなわけよっ![]()
…こういう表現ができるようになると、退団しちゃうのよね、みんな![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1幕ラストを一人歌って〆るというのは、「カサブランカ」と同じ展開。音楽もめっちゃ似ているが、リックは、あの時、「本当のオレ」を求める歌だったな~と、その違いがツボ。どっちも、ずっと愛し続けていた女に逃げられた後で、とすれば、男の本音は、より「ONCE…」なんだろう。プロとして作品を作る中で、これはイケる![]() とイケコが確信した的「カサブランカ」と、オレは何が何でもこの作品を作る
とイケコが確信した的「カサブランカ」と、オレは何が何でもこの作品を作る![]() と願い続けたイケコの夢の結晶的「ONCE…」の違いなんだろう、と思った。
と願い続けたイケコの夢の結晶的「ONCE…」の違いなんだろう、と思った。
それを託された望海の奇跡の舞台を、自分の目で観ることができた…この記憶は、私にとっても奇跡に思えた。
叶わない夢の対象(ギャツビーで言ったらデイジーみたいな…)を具現化する…という難題に挑んだ真彩希帆も、お見事![]() 叶わない夢の対象役と言えど生身の女なので、人生の後半に再会すると、たいてい主人公を幻滅させる存在になるのだけれど、宝塚らしく、うまくいかなかった人生の中で、それでも凛と生きている姿が印象的。その矜持があるとないとでは、舞台の印象が違ってくる。
叶わない夢の対象役と言えど生身の女なので、人生の後半に再会すると、たいてい主人公を幻滅させる存在になるのだけれど、宝塚らしく、うまくいかなかった人生の中で、それでも凛と生きている姿が印象的。その矜持があるとないとでは、舞台の印象が違ってくる。
ブロードウェイのスターを演じるシーンは堂々としていて、実力主義のブロードウェイのステージでセンターに立つ違和感がない。どんな作品であっても、トップコンビが主役を演じる宝塚においては、歌姫のような役を歌の苦手な娘役が演じることも多いが、やはり、歌ウマスターが、歌ウマスターを演じるのは、素直に物語に入り込める![]()
さらに、後半生のデボラを演じる真彩が、キラキラの少女時代以上の説得力を持っていたことが、嬉しい。でも、いい女優になったな~と思った頃に退団発表になっちゃうのよね![]()
![]()
![]()
彩風咲奈については、1958年のベイリー長官の芝居が、もう、泣けて泣けて…![]()
![]()
![]()
今、旬を迎えたな~と感じられて嬉しい。人生の最晩年を演じて、その魅力でもって旬だな~と感じさせるって、芸の世界は面白いですね。
彩凪翔、朝美絢のW3番手は、そのマックスの人生を彩ることで魅力を発揮する。
彩凪は思ってもみない役どころで、決して出番も多くなかったが、思ってもいないくらいの好演。前回の土方といい、今、ノッているのは間違いないようだ。
女役として彩風と組んだ朝美は、セクシーでキュートなスピークイージーのスター姿もよかったが、サナトリウムで記憶を失くして療養している姿がめちゃくちゃ可愛くて、彼女の上だけに歳月が流れていないような、無垢な風貌が忘れられない。
ニックを演じた綾凰華は、なんでそんなに爽やかなの![]() どうしてデボラを愛さなかったの
どうしてデボラを愛さなかったの![]() そうなったら、一番幸せだったんじゃないかな…などと、妄想してしまう爽やかさは、さすが。
そうなったら、一番幸せだったんじゃないかな…などと、妄想してしまう爽やかさは、さすが。
アポカリプスのメンバー、真那春人は、本当に達者だな~と思う。すごい面々と一緒に、青春を駆け抜ける芝居ができた、縣千、彩海せら(あみちゃんは、だいぶ最初の方だけだけど)も、いい経験になったに違いない。
その他の出演者も、みな適材適所で使われていたが、一度の観劇では、目がいくつあっても足りず、もったいない使われ方なキャストも多かった気がする。特に、退団者で長年の功労者である舞咲りん、早花まこの二人は、スポット的な扱いに留まり、まあ、個性的だったから、こういう形でしか無理だったよな…と、しんみりしてみたり。
まんべんなく役を行き渡らせるためには、できるだけ多くのキャストに一場面だけでも見せ場を作って、繋いでいくしかない。そんな悪条件の中で、しっかり印象を残していたのが、94期の両輪、久城あすと煌羽レオ。この二人のいない雪組は、ちょっと想像できないな。
娘役では、幻想の中で天使を演じたというか踊っていた笙乃茅桜の姿が、シュールで印象に残っている。
本当に、貴重な公演を観ることができ、一生忘れられない夜になった。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)



![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
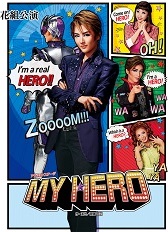


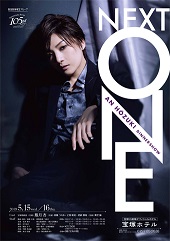




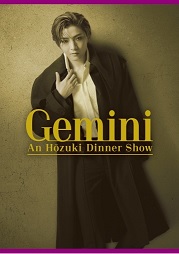
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)


