「日の名残り」観劇 [┣大空ゆうひ]
朗読劇
「日の名残り」
原作:カズオ・イシグロ
訳:土屋政雄
上演台本・演出:村井雄
美術:竹邊奈津子
照明:杉本公亮
音響:清水麻理子(オフィス新音)
衣裳:日下和則
舞台監督:今野健一(キーストーンズ)
照明操作:山口洸
演出部:櫻岡史行、三枝理恵
ヘアメイク:荻野明美、堀川貴世、高橋雅子
大道具(レンタル幕):ファイバーワーク
小道具:高津装飾美術
小道具(燭台):シミズオクト
衣裳協力:INGEBORG、世田谷パブリックシアター
運搬:マイド
制作助手:中村みなみ
チケット管理:菅谷舞
プロデューサー:根本晴美、馬場順子
企画協力:早川書房
朗読劇で複数キャストというのは、この時期、リスクを最大限回避し、短い稽古期間で上演でき、さらにリピートも期待できるため、急速にこの手の公演の上演が増えている。
今年、2公演が中止となってしまったゆうひさんの復帰舞台は、そんな朗読劇となった。
とはいえ、ゆうひさん、けっこう朗読劇をやっているし、私は、ゆうひさんの朗読がとても好き。
会場は、私はわりとおなじみの劇場だが、ゆうひさんご出演としては、初めての会場となる、池袋のあうるすぽっと。入場前にお手洗いに寄って手を洗ってから入場するように、というアナウンスがあり、お手洗い経由で入場。
入口にサーモグラフィーが設置されていて、足元にも消毒のカーペットがあった…かな![]()
チラシと簡易プログラムは、初日は、受付テーブルの上にあったが、受け取れなかった人が多かったのか、次に行った2日には、座席に置いてあった。ロビー内まではチケットをもぎらない劇場なので、そこからあらためて、劇場に向かう階段の前で、チケットを見せ、自分でもぎり、手指消毒をして、座席に。
座席は、1席おきの配席になっている。
舞台には、これも、ディスタンスが十分とられた位置に椅子が4脚。
原作は未読のまま初日を観劇し、翌日、さっくりと購入。
出演は、スティーブンス役に眞島秀和、ミス・ケントン役に大空ゆうひ・小島聖(Wキャスト)、ダーリントン卿・スティーブンスシニア・桟橋の男役にマキノノゾミ、ファラディほか十数約に桂やまと・ラサール石井(Wキャスト)。
大空さんのFCでチケットを取った関係で、私が観劇したのは、すべて、眞島・大空・マキノ・ラサールという出演陣。もうひとつのバージョンも見たかったが、公演期間が短く断念しました…![]()
![]()
![]()
 全員が一緒にステージに登場し、まずは、椅子に座る。
全員が一緒にステージに登場し、まずは、椅子に座る。
そして、眞島が立ち上がって、朗読はスタートする。ごくたまに誰かが立ち上がってセリフを言うくらいで、ほとんど動きはない。
ゆうひさんは、スケ感のある黒のレーシーなコーディネート。
これがもう、シックで可愛い![]()
髪も、ふんわりとした纏め髪で、こちらも可愛かった![]()
←ご覧になれなかった皆様、私のへたくそな絵で、イメージだけでも感じてください![]()
物語は、1950年代を“現在”とし、そこから過去(1920年代~30年代)を回顧する内容になっている。
語り手のスティーブンス(眞島秀和)は、ダーリントンホールと呼ばれる英国貴族の館の執事。現在、館の主は、アメリカ人の富豪、ファラディ氏(ラサール石井)。スティーブンスは、元の主の死後も館を守り、そのまま館ごと、現在の主に仕えることになった。その間、多くの使用人が退職し、昔は17人もの使用人が仕えていた館を、現在は4人で賄っている。
そんなスティーブンスのところに、かつての女中頭、ミス・ケントン(大空ゆうひ)から手紙が届いた。ダーリントンホールを懐かしみ、現在、彼女の結婚生活はうまくいっていないらしい。もしかしたら、再びダーリントンホールで働いてもらえるかもしれない…と感じたスティーブンスは、旅行がてら彼女に再会してみようと考える。
本作は、その一週間ほどの旅の記録に、元の主であるダーリントン卿(マキノノゾミ)との日々の回顧録を織り交ぜたような内容になっている。
ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの代表作といっていい小説を、劇として再構成するというよりは、2時間という枠に収めるためのカットのみで構成していた。
そのため、語り手のスティーブンスに割かれるセリフ量がとにかく多い。
これをほとんど噛まずに語りきる眞島の力量に、まず心が震えた。
スティーブンスが語り手なので、その他の三人が演じる人物たちは、当人ではなく、スティーブンスから見たその人物であり、スティーブンスが語る地の文に続く「 」の部分を喋るみたいなイメージ。
ゆうひさんは、自分のセリフになる少し前、スティーブンスがミス・ケントンについての地の文を読んでいる時にすーっと役としての佇まいになる。出番と出番の間が常にあいていて、四人の中で一番セリフ量が少ないが、ミス・ケントンに関係ない部分では、静かに台本のページを繰っていて、その優雅で優し気な雰囲気も素敵でした![]()
英国の貴族や富豪の家には、執事と呼ばれる使用人がいる。ダーリントンホールは、多い時で17人の使用人を常時雇っていたから、副執事と女中頭もいた。
原作によると(朗読ではカットされている)、ダーリントンホールが、副執事としてスティーブンスの父を雇い入れ、女中頭としてミス・ケントンを雇い入れたのは、それぞれの前任者が、まさかの駆け落ちをしたからだった。朗読劇の中で語られるミス・ケントンは、どう考えてもスティーブンスに恋をしていて、それをスティーブンスが鈍感の限りを尽くしてスルーしているような情景だったが、どうやら、スティーブンス的には、この駆け落ち事件が非常にショックだったようで、その影響が、ミス・ケントンへの頑なな態度につながったようだ。
もちろん、前任の女中頭のことなど、ミス・ケントンは知る由もなく、彼女は、スティーブンスへの恋心を募らせていく。原作によれば、彼女が結婚して屋敷を去るのは、出仕して十数年後、30歳を数年過ぎていたようだ。年齢的なこと、彼女を気に入って結婚を申し込んでくれそうな男性の存在、そして、自分の想い…様々なことを考えて、ミス・ケントンは、賭けに出るようにスティーブンスにモーションをかけているのだが、スティーブンスの鉄壁のスルーは、憎らしいほど。
結婚して何十年も経った今でも、スティーブンスと一緒になっていたら、どんな人生だっただろうか、と思って時々家出するくらい、彼女は、一心にスティーブンスを思っている。完全な片思いではなく、スティーブンスもまたミス・ケントンに惹かれていたし、それに気づいていたからこそ、諦めきれない思いがあったのだろう。
にも拘わらず、ミス・ケントンに会おうと思った最初の動機が、ダーリントンホールへの復帰を打診したいというものだったのだから、スティーブンス、鬼畜![]()
てか、認めろ、好きだったくせに…![]()
![]()
![]()
もちろん、物語は、そんなスティーブンスにとっては淡い恋バナだけではない。
第一次世界大戦後の世界情勢の中、強敵と書いて「友」と読む的な、ライバルの将校を救えなかった贖罪の意識から、知らず、親ドイツ=親ナチスに傾いていくダーリントン卿。
執事としての範を超えずに卿に仕えるスティーブンスの半生は、本人の満足感とはウラハラに、聞くものに「それでよかったのか」と思わせる。
その頑なさ、冷静さが、第三者的に見ると滑稽で、それにスティーブンスは少しも気づいていない。
でも、演じる眞島は、気づいている。気づきながら、プラスアルファの演技をあえてしていないので、ラストの“アメリカ人相手のジョークを練習しよう”となるラストが痛々しくて可愛く思える。
ゆうひさんファン的には、昨年観劇した「鎌塚氏」シリーズの、鎌塚とケシキの関係性を思い出すような、すれ違う執事と女中頭のシリアス版という感じで、ちょっと別の楽しみ方もできたような気がする。
では、出演者感想![]()
眞島秀和(スティーブンス)…英国が世界に誇るイケズな執事。長年ダーリントンホールに仕え、館以外のほとんどどこにも出たことがない執事のスティーブンスが、初老と呼べる年齢になって初めて、一週間弱の小旅行に出かける。その旅行記という形で物語は進行する。が、彼の心はすぐに過去にとらわれ…結果として、回顧録のような様相を呈してくる。
なかなか複雑な構成の小説を、わりとそのまま上演台本にしているのに、語り、会話のそれぞれが、実に、「らしい」感じ。直前に出演していたテレビドラマを見ていた時も思ったが、主役かつ語り手が似合うなぁ~![]() と。
と。
実直&真面目な風貌で、誠実な芝居がピッタリで、なにより、あれだけの文字数をよく語りきったな~と思う。素晴らしかったです。そして、ちょっと心配でしたが、無事に復帰されて、安心しました![]()
マキノノゾミ(ダーリントン卿ほか)…脚本や演出で何度も名前を記載しているが、出演される作品を見たのは初めて。
ポイントとなる三役を重厚に、あるいはコミカルに演じた。
ダーリントン卿は立派な英国紳士だったからこそ、その心の正しさが悲しい結末を招いてしまった。そして第一次世界大戦後の会議では、彼の態度が立派だと賞賛されたのに、第二次世界大戦後には、素人が政治に踏み込みすぎたと批判される…つまり、その辺りで、政治は、駆け引きできる者に引き渡されたんだな…と思ったりした。
そんなことをいろいろ考えさせられる重厚な演技だった。
桟橋の男、という、中で一番軽い役が、心温まる芝居で作品を〆ていた。
ラサール石井(ファラディ氏ほか)…いったい何個の役を演じたんだろう![]() 圧倒された。特に、スティーブンスの車がエンコして泊まることになった家に次々出入りする近所の住人の演じ分けがもう神
圧倒された。特に、スティーブンスの車がエンコして泊まることになった家に次々出入りする近所の住人の演じ分けがもう神![]() 楽しませてもらった。
楽しませてもらった。
大空ゆうひ(ミス・ケントン)…この作品の登場人物は、スティーブンスが旅行で出会った人(1950年代)と、回想に出てくる人(1920~30年代)に分かれるが、ミス・ケントン(ミセス・ベン)は、その両方に出てくる唯一の登場人物だ。
20‐30代の有能な女中頭の部分と、適齢期を逃しかけた女性としてのナマな部分、そして、50代を迎えた女性の落ち着きと知性…一人の女性の色々な面を、短い登場場面で的確に表現していて、久しぶりの大空ゆうひを堪能した。
スティーブンスシニアの臨終付近の有能な女中頭であり、スティーブンスに心を寄せる女性としての優しさに溢れた芝居に、特に心惹かれた。あと、後半の「夫を愛せるほどに成長したのだと思います」というセリフが、心に残った。





![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
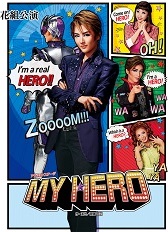


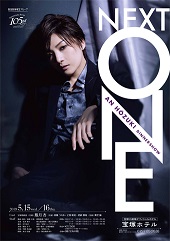




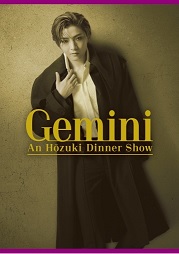
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)


