フィッツジェラルドの午前三時③ [┣宝塚作品関連本等の紹介]
さて、スコット・フィッツジェラルドは、放蕩三昧の人生を過ごしていたわりに、一年ごとの「出納簿」をこまめにつけていたらしい。そこには金銭の出入りだけでなく、人生の決算も纏められていた。仕事はしたかとか、ゼルダとの関係はどうだったかとか、幸福だったかとか。
そして、アルバムならぬスクラップブックを自分の分と妻の分、作っていた。
そこにはありとあらゆるものがスクラップされている。もちろん写真もある。プリンストンで上演された音楽劇「いちばん美しいショウ・ガール」に出演した時の、女装写真まで。
そして、その扮装で、スコットはつば広の日よけ帽をかぶっているとか。
新婚の場面で、ゼルダの帽子をかぶっておどけたスコットには、そんな意味があったかもしれない。
さて、劇中スコットが何度も言うように、「フィッツジェラルドが短篇を書くのは金のためで、その作業は重荷であり、できれば長篇に打ちこみたい」というのが彼の本音であったようだ。
【三章からなる物語を三日間で一気に書きあげ、つぎに一日か一日半で手直しし、すぐに送ってしまわなければならない】
というのは、「美しく呪われた人」に出てくる言葉だ。
ただ、スコット自身は、「サタデー・イブニングポスト」のための短篇を書く「気分になる」のに、平均六週間を必要としたらしい。
が、劇中ローラが語るように、実はフィッツジェラルドの短篇ファンも多勢いる。
フィッツジェラルド自身、すべての短篇を「屑」とは思っていなかったようで、最初の短篇集「フラッパーと哲学者」の収録作品を、「読むに値すると思われる短篇」「単に面白い短篇」「商業的短篇」に分けている。
当時の出版社は、長篇が発表されるたびに、数ヵ月後に短篇集を刊行することで効率的に収益をあげられると考えていた。そのため、フィッツジェラルドは、新しい短篇の中から、最良のものを自分で選んだりしていた。
しかし、ヘミングウェイの最初の短篇集のタイトルは、「最初の49篇」…無作為に最初から49篇をずばっと刊行している。このことにフィッツジェラルドはかなりショックを受けたようだ。
スコットは短篇に価値を見出さないながらも、短篇の難しさについては、十分認識していた。
【短篇では、一通りの衣裳を誂えられる金を持っているだけなのだ。替えの衣裳はない。だから、靴かネクタイでほんのちょっとしくじっただけで、すべてはおじゃんだ】
こんな真摯な執筆態度のフィッツジェラルドに対して、「サタデー・イブニングポスト」誌編集部は、本当にハッピーエンドを望み、フィッツジェラルドの傑作短篇のいくつかをあっさりとボツにしている。
さて、ボツになった作品に「狂った日曜日」というものがある。どうもこの作品は、日本でいうところの「宴のあと」的理由からボツになったらしい。この作品には、宝塚でも取り上げられた有名人がモデルとして取り上げられている。
映画プロデューサー、アーヴィング・サルバーグ(「失われた楽園」)や新聞王ウィリアム・ハースト(「カステル・ミラージュ」)…いずれも小池修一郎作品に登場する。小池先生は、フィッツジェラルドとその時代がかなりお気に入りだったのだろう。
【要するにフィッツジェラルドは、「ドルを愛しながら、自分の芸術にたいしても高度な自覚を保つ」ことが可能だと断言したヘンリー・ジェイムズとは相容れない性格の持ち主だった】
という一節がここにある。
スコットにとって金になる作品は、芸術たり得なかった、という意味だ。
スコットに関するいくつかの本で、必ずヘンリー・ジェイムズが登場する。この作家をご存知だろうか?
私は短大時代の教授がジェイムズ研究家だったために、授業に登場し、実に詳しく知っているが、日本ではそれほど著名な作家ではないような気がする。
…と思って調べてみたところ、意外と翻訳されている作品は多かった。最近、見直されているのかな?大学時代に、「ある婦人の肖像」が英米文学全集にしか載っていなくて、分厚い本を抱えていたのを思い出す。代表作は「ねじの回転」「デイジー・ミラー」あたりかな?
「ねじの回転」は、ブリテン作曲でオペラにもなっているので、そっち方面から知っている人もいるかもしれない。
1919年に亡くなっているので、フィッツジェラルドにとっては、評価の対象となる一時代前の人物ということになろうか。
フィッツジェラルドと似ている点があるとすれば、下品だったり性的だったり反社会的だったりするものには、直截的な表現を避けるところかな?こちらが別の国の言語で読むせいもあって、作者の意図を自分が邪に誤解していないか、心配になってしまう。
フィッツジェラルドは、【自分の両親を満足させる『良質』の文学を書くことと、銀行の口座を満足させる『お手軽な』文学を書くこと】に引き裂かれ、ドス・パソスによると、【こうした精神分裂のせいで、フィッツジェラルドの人生の大部分は地獄となり、最後には、意思と、肉体及び精神のすべての機能が麻痺状態に陥ったのだ】ということになる。
【カプリにて、1925年5月。いま、ぼくの短篇の値段は一作につき2000ドルです。出来栄えはほとんどひどいものになりつつあります】
【カンヌ、1929年9月。目下、この老いぼれの淫売はショートで一発(村上氏によれば、ワンスクリューと書かれているとか)やるたびに『ポスト』誌から4000ドルもらいます。いまや48手(村上氏によれば40種類)を知り尽くしたベテランだからです。若いときには一手だけでこと足りたのですが】
下の一文は、ヘミングウェイに宛てた手紙なので、これが、
「今のオレは娼婦と同じだ」
の元になっていると考えられる。
が、1929年9月をピークにフィッツジェラルドの原稿料は下降の一途を辿る。
アメリカの景気は死に、スコットの文学は需要を失った。
【「終わりがめでたい」話でなければ、もう小説を売るチャンスはまったくない。むかし、ぼくの書いた短篇の大部分の「終わりがめでたくない」ことはきみも覚えているね】
入院しているゼルダに対してスコットが書いた手紙だ。
今日はこの辺で。
給与計算や決算資料の纏めなど。来週は、しっかり今年度の業務に持ち込みたい。
【去年の今日】
家の前の桜が、葉桜になっていたみたい。
去年も、今年も、十分に桜を楽しむことができて嬉しい。
フィッツジェラルドの午前三時② [┣宝塚作品関連本等の紹介]
本日、ソネットのブログが大幅に変わった。トップページからして全然違っている。(このブログを「お気に入り」に入れている方には、何にも変わらないと思うが、同じソネブロ仲間の方には頷いていただけると思う。)
「共通テーマ」の区分もだいぶ変わっていた。
本来なら、新区分で区切り直すべきだと思うが、全部直すのはとても面倒なので、新年度(2006年4月1日以降)のみを変更した。
宝塚に関する内容は、今後「演劇・ミュージカル」という「共通テーマ」に区分することにした。それが、直接舞台に関係ないことだったとしても。
ちなみにこの「共通テーマ」、ブログの各記事の一番下のところに、ひっそりと出てくる。ソネブロのトップから入らない限り、あまり気にすることもない区分かもしれないが、念のため。
というわけで、昨日の続きを。
大都会での成功、という夢を達成したのはよかったが、スコットはいささか当惑してしまった。
“ぼくは最低の記者よりもニューヨークのことを知らず、リッツ・ホテルの使いっ走りのボーイよりも社交界のことを知らなかったから、そんな役割を演じることは不可能だったのに、その事実が証明されないうち、またたく間に、世代の代弁者にして典型的な時代の子という席に座らされてしまったのだ”
そしてさらに、
“アメリカの若い娘の典型を作ったのがぼくの責任だとしたら、その仕事はまちがいなく失敗だった”
とか、1930年過ぎに親戚の娘がフラッパーを気取っていると聞いて、
“ぼくのつまらない若書きを真似しているのだとしたら、彼女に対して寛大にふるまわなければならない―ぼくたちに仕えようとして腕や脚を失ってしまった人に対するように”
と言ったり。
おそらくは、
“ゼルダとぼくはほんとうに現実だったのか、あるいは、ぼくらはぼくの小説の登場人物ではなかったのか、分からなくなってしまうことがある”
という告白が、狂乱の20’sに対するスコットの偽らざる感想かもしれない。
とは言うものの…
「ジャズ・エイジ」という表現の発明者としての権利は執拗に繰り返したそうだ。
実は、ジャズという音楽には殆んど感心がなかったらしいが。
スコットによる「ジャズ・エイジ」の定義は、かなり厳密なものだ。
【この時代は、1919年5月1日、メーデーの騒乱鎮圧に始まり、1929年の株の大暴落に終わる、すなわち、ちょうどほぼ10年間の歳月なのだ】
スコットの伝説の始まりは、【人々に向かって、自分もあなたがたと同じことを感じていると言っただけ】だった、とスコットは語る。それが大きな成功をもたらしたことに、彼は驚愕していた。
そして、自分が人々を欺いているような気分になったらしい。
しかし、大学時代の彼は、自分は歳月の試練に耐える文学と同じくらい、商売になる本を書く才能に恵まれていると語ったことがあった。そして、どちらの道を選ぶべきか聞いたという。
すさまじいほどの自信と、成功者に相応しくないほどの謙虚さが、スコットの中に同居している。
しかし、それは、もしかしたら、「人々が、自分と同じことを感じている」わけではないことを、彼が生涯理解しなかっただけなのかもしれない。
このことに着目すると、彼のその後の人生が読み解けるような気がする。
その後の人生…そう、
【いうまでもなく人生はすべて崩壊の過程である】
と、書くにいたる、彼の人生―青春時代の夢を実現し、ずっと愛してきた女性と結婚した作家が、その女性によって作家としての才能を破壊される、長い物語―。
テーマが登場したので、今日はこのへんで。
今週から、決算後の資料を作っていく。
今回から、部下の子に作らせて自分はチェックを中心にしていこうと思っている。
【去年の今日】
ケロさんの話から、カエルグッズを買った話へ。
退団以来、ずいぶん多くのカエルグッズを買った。最近は少し落ち着いているけれど。友人のまりなさんは、今日も、なにやらカエルをアップしていたような…。
フィッツジェラルドの午前三時① [┣宝塚作品関連本等の紹介]
フランス人作家ロジェ・グルニエ氏がフィッツジェラルドについて書いた随筆「フィッツジェラルドの午前三時」を読んだ。
午前三時というのは、フィッツジェラルドの作品「崩壊」に由来する。
【魂の真暗な闇のなかでは、来る日も来る日も、時刻はいつでも午前三時なのだ。】
上の写真は、この本の表紙。新婚時代のフィッツジェラルド夫妻の写真と、赤い薔薇の花…「THE LAST PARTY」を観た人にはたまらない構図だ。
この随筆は、中身も、あの舞台を観た人が、なるほど~と、膝を打つような数々のエピソードから成り立っている。
というわけで、以下は、この随筆の感想ではなく、そんな共通の記憶の紹介としてお読みいただきたい。直接ドラマに登場するエピソードもあれば、あの場面は、こういう心理から生まれたのか!というエピソードもある。
そして「THE LAST PARTY」をもっと深く楽しめることは、間違いないと思う。
【彼にはひとつの確信があり、それを一度たりとも放棄することも、裏切ることもしなかった。彼にとって、文学を超えるものは何ひとつとしてなかった…】
“ヘンリー・ジェイムズは、彼の時代のもっとも偉大な作家だ。したがって、ぼくにとってジェイムズは、彼の時代のもっとも偉大な人間なのだ”
「夜はやさし」のタイトルは、キーツ「小夜啼鳥に寄せる頌歌」の一節で、冒頭のエピグラフとして、その詩の一行が引用されている。
短篇「作家の午後」の主人公は、人から『なまじ器用なことが命取り』だと言われて傷つき、『そんなふうにだけはなるまいと、苦役囚のように、文章のひとつひとつに身を削る努力をした』と語る。
そして、ヘミングウェイのたやすくものを書く才能について、ヘミングウェイと自分は兎と亀のようなものだと語ったそうだ。
フィッツジェラルドがヘミングウェイを絶賛したのは、その文体によるところが大きいという。(一音節の単語を多用し、しかもラテン語源でなく、サクソン語源の言葉が好んで使われる傾向があった。)…「キミの文体はまったく新しい」
フィッツジェラルドが、どれだけ小説に誠実であったかを語るエピソードがある。
“ぼくは自分の感情に多くを要求した―120もの小説を。だが、支払うべき代償は大きかった。それらの短篇のひとつひとつに、なにかの雫がわずかに一滴ずつ―血でも涙でも精液でもないが―もっと心の奥底から、自分の一滴が投じられているからだ。それこそが、ほかのものにもまして、ぼくが持っていたものだった。”
彼は、「楽園のこちら側」「美しく呪われた人」「華麗なるギャツビー」執筆期間は、それ以外の記憶がまったくないのだという。
あの芝居を観ていると、スコットは、多くの時間を酔って過ごしていたために、それだけ仕事にも不真面目な人物に見えるが、実は、彼の文学への忠誠は、どんな時にも揺らぐことはなかったのだ。
さて、「THE LAST PARTY」では、登場人物を極端に整理しているので、スコットの実人生に大いに関わった人物が出てこなかったりする。
たとえば、スコットの親友、エドモンド・ウィルソンは、ローラ(青葉みちる)の献辞にのみ登場する。「ラスト・タイクーン」の編者として。が、彼はプリンストン時代からスコットとともに過ごした生涯の友だった。
そして、マックスウェル・パーキンスと同様、ビジネスの上でスコットと大いに関わったハロルド・オウバーも出てこない。思うに、作者は、パーキンスにオウバーの役も任せているようだ。
オウバーはスコットの代理人であると同時に、資金提供者でもあった。そう、これ以上金は貸せないと言ったのは、オウバーだったのだ。
さらにこんなエピソードがある。
【1935年ころ、ある人物がオウバーの仕事場に入っていくと、オウバーは泣いていた。手にはスコットがたった今送ってきた原稿をもっていたが、その短篇の最後の方のページは、削除の線だらけで、汚れて、読めなくなっていた。】
ここで、作家フィッツジェラルドのバックグラウンドが語られる。
「THE LAST PARTY」には、父親のことは出てくるが、母親については一言も触れられていない。スコットの母・モリーは、スコットを身篭っている時期に、上の二人の子を流行り病で亡くしているため、生まれたスコットを溺愛した。が、スコットは、この母親をなぜか殺してやりたいほど恨んでいたらしい。母親殺しの小説や詩を何度か書いている。
スコットの母親はアイルランド移民の家系で、父親は古い南部の紳士で、南北戦争では南軍に付いた。つまり、スカーレットとアシュレが結婚したような家に生まれたのがスコットだったわけだ。
フィッツジェラルドは、ニューマンスクール(寄宿学校)時代に、フットボールの試合で「臆病者」のレッテルを貼られたことがあった。その雪辱を果たすためにも、プリンストン大学では、フットボールを志すが、残念ながら体格が足りなかった。
それでも、フィッツジェラルドは生涯母校のフットボールチームを愛し続けた。
そして、チームについての助言を母校に送りつづけた。亡くなった時も、【「プリンストン同窓会週報」に掲載されたチームについての記事にメモを書き込んでいるところだった。】
スコットは、母校で講演をしたいと熱望していたが、叶わなかった。酒に溺れ、もはや忘れられた作家となったフィッツジェラルドの講演など、誰も聞きたくなかったのだろう。が、第二次大戦後、スコットの文学は再評価され、今では、大学の演劇サークル、トライアングル・クラブでは、このクラブを創設したのはフィッツジェラルドなのだ、という伝説まで生まれている。
第一次大戦の折、スコットは名誉ある戦死を夢見て仕官する。
歩兵隊士官となったスコットの教官は、ドワイト・アイゼンハワーだったらしい。
結局、戦争はスコットを待ってくれなかった。英雄になり損ねたことを、スコットはかなり長いことくよくよと考えていたらしい。
そんなスコットに対して、ヘミングウェイはこう言っている。
“お願いだから、戦争に間に合わなかったからといって、くよくよ気に病むのは止めてくれたまえ。ぼくは戦争でなにも見なかったし、なにも役に立つことはなかったんだから。”
あの、アーネストが!である。
長くなるので、今回はこの辺りで。
今日はイベント先の見学に。遠い…でも、すごくいいところだった。海の近くに住んでいるのに、なんでよその海を見て落ち着くんだろうか?
【去年の今日】
「エリザベート」東京初見。
祐飛ルドルフについて、いささか興奮気味に語っている。
今年も、桜はとっくに葉桜になっている。もうすぐ新緑の季節がやってくる…。
(↓)今年の桜は、今、こんな感じ。

「華麗なるギャツビー」 [┣宝塚作品関連本等の紹介]
「THE LAST PARTY」に関連して、フィッツジェラルドの最高傑作、「華麗なるギャツビー」を読んでみた。

- 作者: F.S.フィッツジェラルド
- 出版社/メーカー: 講談社インターナショナル
- 発売日: 1994/09
- メディア: 文庫
この作品は、1991年に宝塚歌劇・雪組で上演されている。
演出は、小池修一郎。彼にとっては、大劇場3本目の作品。バウデビュー作「ヴァレンチノ」の時に、この作品とどちらを発表するか悩んだ、というから、小池にとっては、かなり思い入れのある作品であり、作者だったのだろうと思う。
その後発表された「失われた楽園」という作品は、フィッツジェラルドらしき人物まで登場し、ストーリーも「ラスト・タイクーン」を下敷きにしたような作品だった。
今思えば、現実の世界は、もちろん因果応報ではないわけで、小池は、その空しさをフィッツジェラルドから学び、そういう舞台を好んで制作してきた気がしている。
小説を読んでいると、小池がいかにこの作品に傾倒していたかが、手に取るようにわかったし、読みながら、舞台のシーンを思い出すことも多かった。
というわけで、当時のキャスティングも盛り込みつつ、読み終わったギャツビーの物語を考えてみたいと思う。
ドラマは、すべて、ニック・キャラウェイ(一路真輝)の一人称で語られる。ニックは、ギャツビーの隣人であり、デイズィの親戚である。そして、彼の存在がギャツビーとデイズィを再会させてしまうことになる。
語り手であるニックの物語になってしまわぬように、小池は彼をナイスガイに設定しているが、実際のニックの語り口は少々シニカルなものだった。
さて、この作品が書かれたのは、1924年。スコットは1896年の生まれだから28歳ということになるが、この小説のラスト近くで、ニックが30歳になって呆然とする場面が出てくる。スコットは年を重ねることに、この時点で既に絶望していたのだろうか?
ニックは、いろいろな事情があって単身NYに出てくる。そして、ロングアイランドのウェストエッグにこじんまりとした家を借りる。隣には、豪勢な邸宅があって、そこには、ジェイ・ギャツビー(杜けあき)という青年が住んでいた。
一方、ニックは、NYに知り合いがいた。大学時代の友人、トム・ビュキャナン(海峡ひろき)が、ニックの親戚の娘、デイズィ(鮎ゆうき)と結婚して、同じロングアイランドのイーストエッグに住んでいた。
ニックは、デイズィの友人にしてプロゴルファー、ジョーダン・ベイカー(早乙女幸)と知り合い、また、トムと愛人であるマートル・ウィルスン(美月亜優)の秘密の部屋に招かれたりする。
ギャツビーは、週末になると、盛大なパーティーを開いていた。
そこには、招待されていても、いなくても、知人であっても、なくても、とにかくおおぜいの客が訪れ、全員が派手に騒ぎ、正体をなくして酔いつぶれていた。
ニックは、なかば呆れながらそのパーティーに参加し、そこでようやく主人であるギャツビーと知り合う。ギャツビーは、この街の誰よりも「まとも」に見えた。
やがてギャツビーは、ニックがデイズィの親戚であることを知り、デイズィをこの家に連れてきてほしいと、熱烈に頼み込む。デイズィは、ギャツビーがかつて結婚の約束をした娘だった。が、二人の結婚は許されず、デイズィは、金持ちのトムと結婚した。
デイズィと再会したギャツビーは、二人の失った時間を取り戻そうとする。そして、夫トムと対峙する。
ここで、ラスパに登場したセリフが出てくる。「奥さんはあなたを愛していません。これまでも愛してなかった。奥さんは僕を愛しているのです」
この言葉はトムを逆上させる。が、デイズィをも追い詰める。
「かつてはトムを愛してた―でも、あなたのことも愛してた」
精一杯のデイズィの言葉を、ギャツビーは否定する。
「あなたは、トムを愛したことなどない」と。
ギャツビーが求めたものはいったいなんだったのだろうか?
この世にないものを、あると信じて求めていたのだろうか?
追い詰められたデイズィは、動転している。彼女はギャツビーの車をハイスピードで運転し、マートルを轢き殺した。
というのも、マートルの夫は、自動車の修理工場を経営していて、トムはそこの上客だった。夫は、妻の行動を不審に思ってはいるが、まさか上客のトムの愛人をしているとは気づいていない。
そして、ギャツビーが珍しい車を持っていたので、上記の三者会談が行なわれる直前、友人としてトムはギャツビーの車を借り、ウィルスンの店を訪れていたのだ。そして、その時、マートルは不倫を嗅ぎつけた夫に監禁されていた。
それがトムの車だと信じて飛び出したマートルを、デイズィが轢き殺す。(ある種、因果応報)
ギャツビーはすべてを闇に葬ることにした。が、マートルの夫、ウィルスン(古代みず希)は、トムから、その車の持ち主がギャツビーだと聞いていた。トムもまた、陽気なマートルの復讐をしたかったので、聞かれて素直に教えたのだ。(トムは運転していたのが妻だとは知らない)
ウィルスンはギャツビーを射殺して自殺する。
ギャツビーの哀しい人生を目の当たりにしたニックは、彼の葬儀を請け負う。
が、あれだけ多くのパーティー客は、誰一人ギャツビーの葬儀に来なかった。ギャツビーと共同で、危ない橋を渡って金を作ってきたウルフシェイム(高嶺ふぶき)でさえも。
ギャツビーの父親、ヘンリー・ギャッツ氏(岸香織)が、故郷から葬儀のためにやってくる。悲しみの中に、彼は誇らしげだった。息子がひとかどの成功を収めたと思っているからかもしれない。
埋葬の帰り、パーティー客のひとりが、彼の家の門のところに弔問に来ていた。誰一人、立ち会わなかったと聞いて、その客は呟く。
「かわいそうなやつめ(Poor son of a bitch!)」
あまり上品な言葉ではない。それだけに悲しみを誘う響きだ。
そして、フィッツジェラルドの遺体を前にして、ドロシー・パーカーという人が、この言葉を呟き、顰蹙を買ったそうだ。その場にいた人は、もう誰もこのギャツビーの一場面を覚えていなかったから。
が、ギャツビーの葬儀は、十数年後のスコットの葬儀を予知したようなものだった。「僕には将来を見通す力があるんです」きらきらした瞳の青年を思うと、切なく、哀しい。
ギャツビーの物語を、今、フィッツジェラルド自身と重ねずに読むことは難しい。
スコットは、「金持ちになること」を自分に課したプリンストン時代の思い出をギャツビーに重ねている。デイズィには、金持ちでないばかりに失恋した初恋の娘、ジネヴィラ・キングを。
が、執筆中のリヴィエラで起きた、ゼルダとエドゥアールとの情事は、作品に別の光を当てる。即ち、スコットは、トム・ビュキャナンにも感情移入をしている。そのことが作品をさらに生き生きとさせているし、不思議な客観性も生まれている。
歌劇の最後の方で、デイズィはギャツビーの埋葬に姿を見せる。そのことが作品の翻案を許可した遺族を怒らせたとか、長年の作品ファンを幻滅させたとか言われている。
たしかに、この物語の成り行きでは、デイズィは埋葬に現れる筈がない。(そのためには、マートルを殺したのが自分だと、夫に告白しなければならないからだ。)
それでもあの場面は、たくさんのカラーシャツが放り投げられる場面での無邪気なデイズィと同じくらい、カタルシスを感じる場面だった。だから、あれは、幻…すべての人が現れてほしいと思ったデイズィの幻なのだ、と、解釈したい。それほどに、無表情に赤い薔薇を投げるデイズィは美しかったから。
最後に、悲劇を共有したゆえに、自然消滅してしまうジョーダンとニックについては、皮肉なエンディングが用意されている。ニックは、決してナイスガイなんかではなかった。が、そんなニックの人間臭さが、この物語を「かわいそうなおとぎばなし」から救っている。でも、宝塚では、あの終わり方が相応しかったな、これだけは。
【去年の今日】
「ブロードウェイ・ガラコンサート」について、またまた語っている。
大浦さんの「NINE!」は本当に素晴らしかった~!
それにしても、劇団は和音ちゃんをどうするつもりなんだろう?これだけのシンガーを、なぜもっと本公演でフィーチャーしないんだろうか?(素朴な疑問)
シェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」 [┣宝塚作品関連本等の紹介]
近所の図書館で借りて読んでみた。
シェイクスピアを借りて読んだのは「十二夜」以来。その時と同じ棚にちゃんと置いてあったのが笑えた。図書館って不思議なくらい本の位置関係が変わらないものだな。(「十二夜」を借りたのはバウ公演の時だから、たぶん7年近く経っている?)
借りたのは白水Uブックスのシェイクスピア全集。東京芸術劇場館長の小田島雄志氏が訳したものだ。
それにしても、本当に男しか出てこない芝居である。
女性の役は、ブルータスの妻・ポーシャがちょこっと出てくるだけで、シーザーの妻・キャルパーニアなどは、ほとんど端役レベルだ。そして、それ以外の女性は出てこない。このまま舞台化したら、娘役ファンとしてはちょっと許せない気分になると思う。
さて、この「ジュリアス・シーザー」は、様々な史料から1599年初演ということが確認できるそうだ。日本でいえば関が原の1年前。「野風の笛」の時代…。
シェイクスピアは「ヘンリー五世」を書き、この「ジュリアス・シーザー」を書いて、さらに「ハムレット」を書いた。そして、「ヘンリー五世」の凱旋はジュリアス・シーザーのそれを模して描写され、「ハムレット」には、ポローニアスが大学時代に「ジュリアス・シーザー」を演じたことがある、というセリフがあるそうだ。
これは解説にある通り、実際にポローニアス役者がその前にシーザー役者だったことを言っているように思う。つまり「楽屋落ち」というやつだ。
もしそうだとすると、ジュリアス・シーザーを演じる役者は、ポローニアスクラスの俳優ということになる。スターシステムをとっているわけではないので、断言はできないが、それって主役じゃない役者ってことじゃないのかな?
出番もそれほど多くはない。
そして、どんな人物か、読んでいてよくわからなかった。心の内を見せる部分がないというか…。
シェイクスピア時代の芝居は、独白でなんでも語ってくれる。
宝塚でいえば柴田先生の作品に出てくる、録音で流れてくる内心というヤツがセリフとして登場する。これはどうも、正面を向いてしゃべったらセリフで、横を向いてしゃべったら傍白というふうに区別されていたらしい。
そういう傍白のない役なのだ、シーザーは。
一方、ブルータスやキャシアスは、傍白あり、独り言あり、気が大きくなったり、不安に苛まれたり、まさにシェイクスピアの主役らしい動きをする。
そしてマーク・アントニーは、「ベニスの商人」におけるポーシャのような機転のきくキャラクター。
シェイクスピアの時代、誰が主役だったかはわからないが、現代人の感覚で読み解けば、この芝居は「ブルータス」という悩み多き人物が主人公になる。
シーザーは、「マクベス」におけるダンカン国王の役割であり、キャシアスがマクベス夫人ということになろうか。
アントニーの演説が見せ場、ということを事前に聞いていたので、その後の戦闘と死は蛇足のように見える。
キャシアスは、「アントニーを殺すべきだ」と主張するが、ブルータスはこれを虐殺だとして、否定する。そして追悼演説を希望するアントニーに対して、これを許し、しかも自分はアントニーに自由に演説をさせて立ち去ってしまうのだ。
こう書くと「ツメが甘い」ブルータスと思われるかもしれないが、彼はクーデターを起こしたつもりがまったくないのだ。(もちろんキャシアスは、これがクーデターであると思っている。)
ブルータスは、シーザーの専制がローマのためにならないから殺害しただけで、その後、ローマを牛耳るつもりがまったくないのだ。どうやら「バカ正直」なキャラクターであるらしい。
しかも、戦闘の指揮能力も低く、あっという間に敗北を喫する。
その死後、アントニーはブルータスだけは高潔な魂の持ち主だったと褒めるのだが…ビジョンがないのに指導者を暗殺するっていうのは、迷惑なだけのような気がする。
キャシアスは、自分にはブルータスほどの人望がないのを知っていたので、彼を担ぎ出し、ブルータスさえ目を覆う専制だったのだ、という形でシーザー暗殺を正当化し、あわよくば次の実権を狙っていたのではないか?
だから、シーザーとともにアントニーも殺してしまいたかったのだと思う。
が、ブルータスは、傀儡で終わるような人間ではなく、愚直なまでに自己を押し通し、その結果、キャシアスを含むすべての人々を死に追いやった。ただ、その心は高潔だった、という人物。
アントニーは、シーザーの腰巾着。が、それだけで終わらない器量も持っている。シーザーの死後、命の危険を回避した上で、さらに立場を逆転させる大演説をぶったのは、正義の士だからではなく、なかなかの策士であったから。
オクテーヴィアスは年が若いにもかかわらず、シーザーの養子(妹の孫なので血縁関係はある)にして、後継者という立場を十分に理解している。だから、狡猾なアントニーに対しても、一歩も引かずに接している。
なんだか、ステキな役が一個もないような…。
もちろん、演じがいのある役ばかりだと思うのだが、宝塚の主役としてうっとり眺められる役がないなーと思う。
どんなふうに改変されるのか、じっくりと見極めたいと思う。
シェイクスピアは、ブルータスの演説を散文で、アントニーの演説を韻文で書き分けたという。アントニーの演説はたぶん歌になると思うのだが、どんな名調子をきりやんに歌わせてくれるのか、それだけは、楽しみなのである。
歌詞は別にして。
【去年の今日】
決算で身も心も疲弊したのか、たった一行だ。
でも「明日は休めそうだ」と書いてある。え?今年より、マシ?
阿倍小足媛のその後 [┣宝塚作品関連本等の紹介]
こんな本を読んだ。
石上朝臣麻呂は、天智天皇の側近でありながら、壬申の乱を生き抜き、70歳以上の天寿を全うした、この時代には珍しい人物。
「飛鳥夕映え」よりは、少し時代が下って、近江朝~奈良時代までの話だ。
が、もちろん「夕映え」の登場人物も出てくる。そして、とんでもない記述を発見してしまった。軽皇子は、中臣鎌足を味方につけるために、妻の小足媛に鎌足の伽をさせた…と。
こ、、、これは、作者の創作?それとも歴史的事実?
どちらにしても、小足媛と石川麻呂のエピソードは、柴田先生の創作のはずだし、おちつけ、自分…と思いながらも、
う…うらやましいぞ、小足媛!
宝塚をご存知ない方には、わからない話ですね。すみません…
中臣鎌足・軽皇子・蘇我石川麻呂は、そのお芝居では、とってもステキだったんです。史実はどうであれ…。






![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
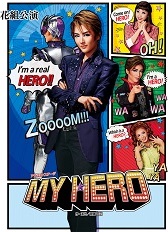


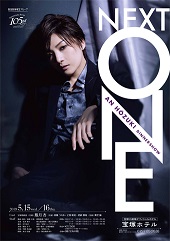




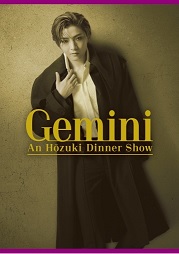
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)


