「ボーイズ・イン・ザ・バンド」東京凱旋公演観劇 [┣演劇]
「ボーイズ・イン・ザ・バンド~真夜中のパーティー~」
7月にシアターコクーンで上演された「ボーイズ・イン・ザ・バンド」が、全国各地を回って東京に凱旋した。その初日を観劇。コクーン上演時の感想はこちら。
結末を知ったうえで観た凱旋公演は、作品に深みが増したこともあって、観ていてえぐかった。
同じ作品で、こんなに受ける印象違うのかな…![]() と。
と。
さて、上演された、なかのZERO大ホール、演劇を観るために中野に通うこと、おそらく100回を超えている気がするが、お初の劇場でした![]() 南口に降りて左に向かったことなかったもんね
南口に降りて左に向かったことなかったもんね![]() (南口はポケットスクエアしか行ったことない…
(南口はポケットスクエアしか行ったことない…![]() )
)
感染症対策内容は、シアターコクーンと同じ。
劇場が…というより、主催が対策の大枠を決めているのかな、と思った。
ただ、この劇場は、舞台後方に搬出口がないのか、開演まで背景をオープンにしているということはなかった。
さて、このお芝居のタイトルの「ボーイズ・イン・ザ・バンド」、別に演奏するわけでもないのに、なんでバンドなんだろう…と、ずっと不思議だった。(“~真夜中のパーティー~”の方は、1970年に映画化された際の邦題。実際、真夜中にバースデー・パーティーが開催されているのだから、これ以上ない分かりやすい邦題だと思う。)
このタイトルは、映画『スタア誕生』(1954)の中で、取り乱したエスター(ジュディ・ガーランド)に向けてノーマン・メイン(ジェームズ・メイソン)が、“You're singing for yourself and the boys in the band.”と諭したセリフから取られているのだとか。
「バンドのやつらのために歌え」の意味は、表に出ている人間は、その後ろ側にいる大勢の人々のために声をあげる必要がある、ということだろうか。1968年、社会的に居ないもののように扱われ、あるいは治療の必要がある病人のように扱われている多くのゲイたちのために、彼らがたしかに、あらゆる社会の中に、生きて悩んでいることを伝える使命がある。劇作家として、マート・クロウリーは、そんな風に考えたのだろうか。
さて、本作は、1968年に初演の作品ではあるが、2018年にブロードウェイで上演され、トニー賞の演劇リバイバル作品賞を受賞している。その時の出演者は、全員がオープンリー・ゲイ俳優(ゲイであることをカミングアウトしている俳優)だったという。
最近のエンタメ業界では、(特に米国では)その役の特性と合致した俳優を起用することが是とされていて、たとえば、聾者の役であれば、聾者の俳優を使うべきだし、トランスジェンダーの役であれば、トランスジェンダーの俳優を起用すべき…という意見が主流となっている。オープンリー・ゲイの俳優も多く存在することから、このような起用ができたのだろう。
翻って日本では、まだまだそのような風潮には程遠く、そもそもオープンリー・ゲイの俳優が非常に少ないので、これが適用されると、本作など上演ができなくなってしまう。それに、日本の演劇事情として、ある程度テレビ等で著名な俳優を出演させないと、興行として成り立たない(特に地方公演)ということもある。
とはいえ、俳優たちの方は、海外のキャスティング事情なども十分見聞きしているので、オファーを受けた時点で、主演の安田顕、パーティーの主役・鈴木浩介は、やはり躊躇したらしい。やってみたい、でも、やっていいのか、と。
私は、今の日本の芸能界では、役としてゲイを演じるという形で広く男性俳優にオファーしたという今回の形態は正しかったと思う。もしかたら渡部豪太が演じたバーナードは、アフリカ系の俳優に演じてもらうと、分かりやすかったかな、とも思うが、演技の質の合う俳優がうまく当て込めるか、と考えると、選択肢が広いわけではないので、難しかったかもしれない。
では、凱旋公演だからこそ感じられたかもしれない感想を書いていこうかな。
マイケル(安田顕)とドナルド(馬場徹)だけの場面から始まるのだが、そこの印象が全然違った。コクーンでは単なる導入部としてほとんど聞き流していたところに、それぞれのキャラの根幹となるキーワードがたくさんあった。これを知っただけでも、凱旋公演を観られてよかったと思う。
そして、ドナルドが好きだ~![]() と唐突に感じた。一回ラストまで観たからこそ、このスタンスでマイケルと一緒に居てくれるドナルド神
と唐突に感じた。一回ラストまで観たからこそ、このスタンスでマイケルと一緒に居てくれるドナルド神![]() ってなる。てか、一回ラストまで観ると、このボーイズたちへの感情移入が出来上がっていて、マイケルに自分が同化しちゃってる部分がある。なので、ちょうどいい距離感で側に居てくれるドナルドは、もうそれだけで愛しいんだと思う。
ってなる。てか、一回ラストまで観ると、このボーイズたちへの感情移入が出来上がっていて、マイケルに自分が同化しちゃってる部分がある。なので、ちょうどいい距離感で側に居てくれるドナルドは、もうそれだけで愛しいんだと思う。
そういう意味で、エモリー(浅利陽介)にもウザさを感じないし、彼女がオネエ語を隠さなくなるポイントもハッキリと分かって、ああ、最初にアラン(大谷亮平)の方がケンカ売ってるんだな~と納得。初回では、マイケルに感情移入はしていないながら、主役であるマイケルの立場に立って観ていたので、アランにバレないようにしなきゃならないのに、非協力的だなーと、非難の目で見てしまったんだなと思う。
エモリーたちが登場すると、一気に情報過多になるが、そこも、後の情報を知っていると、さらに興味深い。
ラリー(太田基裕)は、ドナルドと、一度サウナで愛を交わしたことがあるが、その時は、会話もなく名乗りもしていないので、会った瞬間、二人同時に固まる。それはつまり、お互い、かなり気になっていたということなのだろう。そのラリーの様子に、恋人のハンク(川久保拓司)はすぐに気づき、態度を硬化させる。ここからハンクとラリーは、ずっとギクシャクしている。だからこそ、告白からのラブラブ展開が感動的なんだな~![]()
アランが登場した時、異質物の来訪に、全員が緊張する中、いち早くウェルカムな姿勢を取ったハンクは、ひとつには、自分ならアランと違和感なく会話ができるだろうという大人の判断、もうひとつには、ラリーとドナルドへの当てつけという子供っぽい嫉妬心があったんじゃないかな。
ここからラリーは、遠慮を捨てて、けっこう長い時間、ドナルドと飲みながら会話を楽しんでいる。間にカウンターを挟んでいるのは、これ以上の深入りをしない、という意思表示かもしれない。恋人がいても、セックスの相手は自由に選びたいと考えているラリーにとっては、貞節を示すためには、「知り合いには手を出さない」ことが重要なのかもしれない。それでも、見つめ合い、緩やかに時を過ごそうとするのは、よっぽど「タイプ」なんだろうな、性的な意味だけでなく。
バーナードは、登場した時から、ちゃんとセリフを聞いていると、彼が黒人であることを示唆するセリフがたくさん出てくる。でも、それらのセリフより、渡部豪太である視覚情報の方が強かったんだな~![]() もちろん、「俺は黒人だから」なんてセリフ、普通出てこないし、(アメリカの劇場なら見ればわかる)示唆するセリフで気づくべきだったんだろうが、初見では難しい。翻訳劇ならではの難しさを強く感じる。
もちろん、「俺は黒人だから」なんてセリフ、普通出てこないし、(アメリカの劇場なら見ればわかる)示唆するセリフで気づくべきだったんだろうが、初見では難しい。翻訳劇ならではの難しさを強く感じる。
アランは謎多き人物だ。
NYに来るなりマイケルに電話を入れ、泣きながら会いたいと言う。そのあとまた電話がかかってきて、明日の約束を取りつける。が、実は、その電話は下の公衆電話からかけていて、その後、マイケルの部屋に現れる。そこでパーティーが開催されていることを知っていながら。しかも、彼はタキシードを着ている。行かなくてはならない場所があるから、その前に少しだけ会いたかった、と言う。でも、マイケルが勧めると、断らずに酒を何杯も飲む。行かなくていいのかよ。いや、そもそもパーティーなんてあったの![]()
アランは、マイケルの大学時代の友人だ。大学はカトリック系で、マイケルは、もう一人の友人、ジャスティン(男性)から、当時、自分がアランを好きだったこと、酒に酔って関係を持ったこと(事実かどうかは不明)を聞かされている。アランは、その時まで、ジャスティンのことをめちゃくちゃ褒めていたらしい。今回も、初対面のハンクを(それ以外のメンバーが彼に敵意むき出しだったから無理もないが)めちゃくちゃ褒めている。
無自覚に男に惚れやすい人なのかもしれない。
マイケルとアランは、アランがNYに来る時には会っているようで、マイケルは、大学時代にはゲイであることを自身で認めていなかったこともあり、今でもアランにはカミングアウトしていない。
アランは、ゲイに対して、当時としては当然かもしれないが、偏見がある。それはホモフォビアとも見える。
そんなアランに対して、マイケルは、お前は本当はゲイで、ジャスティンが好きだったんだろう![]() と決めつけ、彼に電話して告白するように強要する。アランは自宅に電話して、妻に愛していると告げ、パーティーを辞するのだが、彼の来訪は、いったいなんだったのだろう
と決めつけ、彼に電話して告白するように強要する。アランは自宅に電話して、妻に愛していると告げ、パーティーを辞するのだが、彼の来訪は、いったいなんだったのだろう![]()
演劇的には、ある集団の中に闖入者が一人入ることで、集団が見て見ぬふりをしている欺瞞が明らかになっていく…というスタイルの芝居は、よく行われており、これもそのスタイルの演劇ということができる。
でも、芝居の最後、マイケルとドナルドだけになった時、ドナルドがイミシンなことを言う。彼は何のために来たんだろう、なぜ、もっと早く帰らなかったんだろう、と。
私たちは、この演劇の中で、結婚し、二人の子供に恵まれ、なのに40歳を過ぎて、突然ゲイに目覚めたハンクの物語を聞かされている。アランがそうであった可能性は否めない。彼は、マイケルのセクシャリティには既に気がついていて、マイケルの友情を愛だと思い込んでいたのかもしれない。
そして今夜は、マイケルのゲイ友の前に華々しくデビューするつもりで、タキシードでやってきたとか。けれど、そこに彼の居場所はなかった。彼が想像していた男同士の崇高な世界はなかった。彼が求めていたのは、ゲイ仲間じゃなくてホモソーシャルな場所だったのかもしれない。そして、アランは、自分が非情にも捨て去ろうとしていた世界に帰る決心をする。
でも、その最後のキッカケは、ジャスティンのことかも。アランは、ジャスティンじゃなく、ずっとマイケルが好きだったのに、ジャスティンのことを誤解して、それを自分への攻撃材料に使ってくるマイケルにショックを受けたのかも。あと、来た時から、アランはマイケルをミッキーと呼んでいて、それをやめてくれ、って言われたのも地味にショックだった気がする。だって何十年もそう呼んできたと思うし。自分だけに許された呼び方だって信じていても不思議じゃない。なのに…![]()
![]()
![]()
こんなふうにアランについて深く考える(ほぼ妄想)ことができたのも、2回目の観劇ならでは…だったが、ラリーとハンクについても、2回目ならではの感想が出た。
ラリーの考え方って、すごく21世紀的なんじゃないかな。もちろん出会ってすぐ関係を持つことの感染症的な危険性についての認知は、さすが1968年で、その辺は、脇が甘いなって思うけれども。(当時は肝炎くらいかな。エモリーのセリフにありましたね。)
でも、パートナーがいたとしても、性の自己決定権は留保していいっていうのは、21世紀的だ。
「キミのことは愛してる。だけど、今夜僕と寝たいと言われても、僕が今夜キミと寝るかどうかは、ボクにも選ぶ権利があるよ」
こんなふうに言い表せば、ラリーの考え方は、現代人にも理解されやすいかも。現実的には、僕が今夜キミと寝るかどうか、というよりは、僕が今夜誰と寝るか、なので、たぶん納得性は低いけど。でも、まあ、パートナー間で貞節が重要視されるのは、そもそもは子供の父親を特定したいということに始まったのだから、生殖を目的としない性的関係においては、貞節は第一条件ではないとも言える。その辺は、男女の結婚を経験しているハンクの固定観念が二人のネックなのかな。
自信に溢れたハンター、ラリーは、それでもハンクをすごく愛していて、その心と体のギャップがラリーを魅力的に見せている。とはいえ、東京凱旋公演では、フリーなラリーくんがだいぶハンクにつかまっちゃったな~![]() という印象も受けた。やはり、長い公演期間、情が移っちゃうのかな。
という印象も受けた。やはり、長い公演期間、情が移っちゃうのかな。
ハンクのヘアメイク、コクーンより老け気味でしたね。ラリーのせいで年取ってしまったのかしら![]()
ハロルドが登場してからの深いテーマは、まだまだ受け止めきれなくて…もっともっとこの戯曲からは学ぶことがたくさんあると思った。ハロルドがマイケルを諭す場面は、痛さが倍増。毎日、こんなん言われてる安田顕氏、大丈夫かしら![]() 自分が言われているんじゃないと分かっていてもつらひ…
自分が言われているんじゃないと分かっていてもつらひ…![]()
「十二人の怒れる男」は、「ボーイズ…」を遡ること10年以上前の作品だが、互いを知らない12人の男たちの、それでも各々の人間性の根幹にかかわる激しいセリフの応酬は、本作に似ている。それを狭いゲイ社会の9人のゲイたちに仮託したような、そんなワンシチュエーション劇だった。
「十二人…」は、毎年どっかで上演されている人気作なので、「ボーイズ…」もそんな作品になればいいな~と思う。絶対観て損はない戯曲。
それにしても、力のある作品に体当たりした出演者の皆様、本当にお疲れさまでした![]()




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
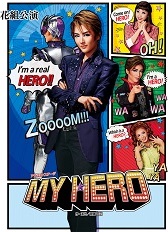


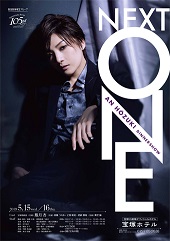




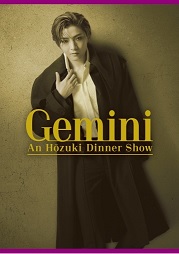
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0