スタジオライフ「言葉の奥ゆき」 [┣Studio Life]
Jun企画
「言葉の奥ゆき~回帰~」
構成・演出:倉田淳
美術・照明・舞台監督:倉本徹
演出助手・照明操作:中作詩穂
音響操作:鈴木宏明
収録・編集:永井純
配信:彩高堂
協力:竹下亮(OFFICE my on)、宮本紗也加、東容子、小泉裕子
企画制作:Studio Life
「言葉の奥ゆき」シリーズも4回目らしい。(3回目、いつだったんだろう![]() )
)
今回は、次回公演(演劇)を延期して何もなくなってしまったところに、朗読を入れることで、劇団活動の始動としたもので、少人数でソーシャルディスタンスを守りながら行える朗読は、他の舞台でも取り入れられているが、スタジオライフの強みは、もともとこのシリーズが存在していたことだろう。
そして、今回は、感染拡大を危惧して劇場に来れないファンのために、配信も用意されている。(配信特典映像もあるらしい。)→https://theatre-live.myshopify.com/blogs/nextevent/kotobanookuyuki
(1公演2,500円)
配信は、全公演終了後から始まるので、どんな感じかはわからないが、劇場で聴く(4,500円)のと同じなら、かなりお得なんじゃないだろうか。
今回の朗読内容は次の通り。
藤原啓児…「接吻」(江戸川乱歩)
倉本徹…「メキシコのメロンパン」(皆川博子)
笠原浩夫…「継子」(夢野久作)
石飛幸治…「鋏と布と型」(久坂葉子)
大村浩司…「人の顔」(夢野久作)
楢原秀佳…「扉の彼方へ」(岡本かの子)
山本芳樹…「水色の煙」(皆川博子)
曽世海司…「薔薇密室」(皆川博子)
青木隆敏…「江川蘭子」(江戸川乱歩)
関戸博一…「入梅」(久坂葉子)
松本慎也…「ルルとミミ」(夢野久作)
今回の倉田さんの挑戦としては、太宰封印らしい(笑)あと、モーパッサンとO・ヘンリーも。
私は、この中で、笠原、石飛、青木、関戸の4人の朗読を聴いた。以下、順に感想を。(感想は聴いた順です。)
「入梅」(久坂葉子)
関戸は、少し丈の短いカジュアルパンツから素足で靴履いてて、わりといつもこんな感じだよね…なんて思う。(素足に靴=どうしても石田純一を思い出してしまう。)
冒頭の地の文から、ぐいぐいと脳内に情景を呼び起こしてくれるのは、作者が誰であっても変わらない。
物語は、戦後しばらくした頃の関西が舞台。
何不自由ない地主の息子と結婚した語り手が、戦後、「絵ざらさ」(よくわからないのだが、布地に絵を描いてテーブルセンターや日傘やネクタイなどに仕上げているらしい)で生計を立てている。一人息子の行雄と、じいやの作衛の三人暮らし。作衛には妻の“おはる”がいたが、関節炎に苦しみ2年ほど前に亡くなった。
最近仕事が忙しくなった語り手は、仕事の手伝いをさせるため、一人の若い女を雇ったが、その名が偶然、“おはる”だった。そして、作衛とおはるは、語り手の目を盗み、いつの間にか男女の仲になっていた。おはるは足が悪く、それが、名前とともに亡妻を思い起こさせるのかもしれなかった。
ある日、おはるの母親がやって来て、おはるの縁談を持ち込む。おはるはすっかりその気で、そのまま母親と一緒に出て行ってしまう。残された作衛は荒れた。その後、おはるの新婚の家にも行ったらしい。おはるの苦情を受け、語り手は作衛が悪いと断じる。
その後、作衛のせいで離縁された、とおはるがやって来る。責任上、語り手は作衛に暇を出すことになるが、作衛は、おはるが離縁された理由を推察し、彼女の不自由な足と、子供ができないことが原因だろうと言う。真実がどうであれ、もう決まったことなので、ひとりぼっちで生まれ故郷の熊本に帰っていく作衛。
そんな物語が淡々と語られる。
語り手の乾いた語り口に、彼女の「持っているもの」と「持っていないもの」が透けて見える。
住むに困らない自身の家があり、家族を養える仕事があり、それも前途洋々らしい。一方、話し相手になる存在もなく、若い身空で、未亡人。もう二度と夫に甘えることも、誰かと肉の交わりを持つこともない。(願望はあっても、彼女の自尊心がそれを許さない。)
その苛立ちで物語を終わらせるところと、作衛への憐憫が通り一遍なの(あと、息子への偏愛がこの先大変だな~ってのも)を含めて、作者の語り手への悪意も感じられる。それでいて美しい文体なのだ。
関戸の朗読は、そんな作者&語り手の意地悪さをも巧みに表現しながらも、華美な表現ではなく、こちら側に決定権を委ねるような、しなやかな語り口。ああ、だから、この作品は、関戸なんだな~と、倉田さんのキャスティングに納得した。
「江川蘭子」(江戸川乱歩)
一方、青木は、実に演劇的に「江川蘭子」を紹介した。
生まれながらに毒婦の要素を持つ“江川蘭子”の一生を紹介するのかと思いきや、彼女がまだ16歳くらいのところで、突然、この先のことはしーらないっ![]() と投げ捨てる江戸川乱歩、何があった
と投げ捨てる江戸川乱歩、何があった![]()
女妖江川蘭子の悪魔の生涯も、恐らくは彼女の赤ちゃんであった時代の世にも奇異なる環境のせいであったに違いない。
とか、
この老人こそ、江川蘭子の悪魔の生涯の、謂わば一種のポイントマンであった。
と書きながら、ラストは、
だが、彼女はまだ老い先長い十六歳の小娘だ。年と共に、彼女の胸に咲き乱れるであろう悪の華が、如何に毒々しく美しいものであるか。年とし長ちょうじてどの様な妖婦となり、年老いて如何なる悪婆となるか。彼女が第一に行う大犯罪はそもそも何事であるか。又この女悪魔を向うに廻して闘うものは誰か。或は飜然ほんぜん悔悟かいごして、和製女ヴィドックとなるか。それとも又、江川蘭子は忽然姿を消し去って、全く別の人物が舞台を占領するか。凡て凡て、この作者は何も知らないのである。
「悪魔の生涯」ってなんだったの![]()
ちなみに16歳の時点では、小悪魔的なことはやっているものの、殺人など犯罪は一切行っていない。
なにか、長編を書くつもりが、途中で飽きて投げ出してしまったような、あるいは、こんな話、連載は無理です![]() と編集部に切られたか…
と編集部に切られたか…![]()
少女、江川蘭子の愛くるしいように見えながらも、どこか尋常ならざる雰囲気が、芸なのか、自然になのか、青木は見事に出してくる。
その他のキャラクターも、実に演劇的。そもそも地の文からして、おどろおどろしい雰囲気たっぷり。前のめりになって楽しく鑑賞した。
途中、立ち上がったのは演出かと思ったが、青木自身が盛り上がって立ち上がってしまったらしい。
スポットライトがその動きをしっかり追っていたのが、劇団というあ・うんの世界だな~としみじみ。
「鋏と布と型」(久坂葉子)
石飛は、短いスポーティーなパンツに、カウボーイブーツ。
この作品は、戯曲。石飛は、ト書きも読む。登場人物は二人![]() というか、一人の女と一体のマネキン。女は、谷川諏訪子というファッションデザイナー。彼女は、自分の仕事にプライドを持っていて、成功者であり、家庭的にも恵まれていて、自分中心に世界は回っていると思っている。
というか、一人の女と一体のマネキン。女は、谷川諏訪子というファッションデザイナー。彼女は、自分の仕事にプライドを持っていて、成功者であり、家庭的にも恵まれていて、自分中心に世界は回っていると思っている。
オートクチュールのスーツが着られなくなったという電話にも、「太ったあなたが悪い」と言ってしまうくらい。
それを、マネキンがあざ笑う。そして、マネキンが人間を憐れむ。それを聞いているうちに、諏訪子の中にどんどん不安が高まっていって…という、短いが、皮肉に満ちた戯曲。
これ、ゆうひさんが演じたら面白いんじゃないかな…と、聴きながら思った。
マネキン役は、踊るシーンがあるので、ダンサーの人に動きをやってもらって、声は声優さんにやってもらってもいい。想像は膨らむ。
でも、終演後、このセリフのやり取りは、かなり病む…みたいなことを石飛氏が話していたので、トーンダウン。とても面白い作品に感じられるけど、何かを生み出す人には、これがキツいのかもしれないのか…![]()
そして、この作品は、そうして自分を追い込んだ久坂の、最期に向かっていくひとつの道筋だったのかな…と感じた。(最後の作品ではないが、久坂が阪急電車に飛び込んで亡くなった月に発表されている。)
二人の女性の本音トークを一人で演じ分ける様は、石飛らしく、容赦がない。「これはトビちゃんに…」と思った倉田さんは、さすがだなーと思う。
「継子」(夢野久作)
こちらは、普通の朗読作品。
主人公の玲子は華族(子爵)の令嬢なのだが、継母の大沢竜子宛に、前の夫だという男から手紙を預かったことから、恐怖に苛まれる。そして、急に家に来なくなった家庭教師を頼って手紙を送るのだが、真夜中に目が覚めてしまい、起きて外を眺めていたところを継母に見つかり、叱られる。そして、不安の理由を答えるうちに、手紙を渡すことになる。継母は、手紙を音読して、“こんなケチなユスリにかかってビクビクするような子爵夫人じゃないんですからね”と啖呵を切るが、そのしばらく後に殺害されてしまう。
そして、そこへ現れる家庭教師の中村先生。
現代からすると、絶対怪しいわ、中村先生…と思うが、彼は本当に正義の味方だったらしく、ここから謎解きが始まってハッピーエンド。
お話自体がとても面白く、笠原が読んでいる、ということを忘れて、楽しめた。
倉田さんは、「グッド・バイ」の時の永井キヌ子がすごかったので、この竜子役も期待していた、という。もちろん、「 」内部分は、セリフのように読まれるのだが、そこだけが突出していない、ちゃんと悪女と二枚目を演じ分けているけれども、地の文も大事に読まれていて、聴きやすい朗読だった。
終演後、出演者と倉田さんとの短いトークがあった。
両日読まれた久坂葉子は、19歳の時に芥川賞の候補となり、21歳の大晦日に阪急電車に飛び込んで生涯を終えた。50年以上前のことだ。私はこの作家のことをまったく知らなかったのだが、倉田さんは高校生の時に初めてその名を知って興味を持っていたらしい。
時期的に「自殺」がセンシティブ・ワードになっている感じで、出演者(石飛・関戸)が言葉を選んでいるのが、印象に残った。(倉田さんは、初日、普通に語っていたけど、次の時は、なんとなく意識していたみたいで、“自殺”とは言っていなかった。)
四人とも、この自粛期間で、自身のキャリアのこと、演劇のこれからのこと、いろいろ考えたらしい。それは、年齢が若ければ若いほど、悩みは大きかったようにも感じた。演劇はなくならない![]() という力強い言葉は、シニアと…なにより、倉田さんが一番確信を持っていたように感じた。
という力強い言葉は、シニアと…なにより、倉田さんが一番確信を持っていたように感じた。
この調子で、次回公演になだれ込むであろう、倉田さんのパワーが、今は心強く感じる。
これから、配信版を見るのも楽しみ![]()




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
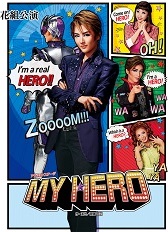


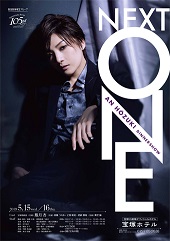




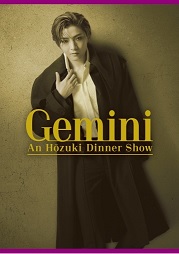
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0