宝塚歌劇星組東京公演「霧深きエルベのほとり」観劇 [┣宝塚観劇]
Once upon a time in Takarazuka
「霧深きエルベのほとり」
作:菊田一夫
潤色・演出:上田久美子
作曲・編曲:入江薫、青木朝子、高橋恵
音楽指揮:佐々田愛一郎
振付:御織ゆみ乃、若央りさ
殺陣:清家三彦
装置:新宮有紀
衣装:有村淳
照明:勝柴次朗
音響:実吉英一
小道具:下農直幸
歌唱指導:ちあきしん
演出助手:谷貴矢
舞台進行:香取克英
初演は50年をはるかに超える昔。
今回、すごく好評で、菊田一夫すげー、もっと菊田作品を![]() という声をあちこちから聞く。
という声をあちこちから聞く。
でも、それは、潤色・演出の上田久美子先生がすごいのであって、元作品は、ふつーに読めば、壮大なやり逃げドラマだよ~![]() なんて、思っていた。観劇するまで、ずっと。
なんて、思っていた。観劇するまで、ずっと。
私は、以前にも「壮大なやり逃げ」というフレーズを使っている。それも菊田先生の作品だった。
「やり逃げ」とは、つまり、主人公の男が、ヒロインと出会い、恋をして、結婚に至らない状態で、肉体関係を持ち、諸般の事情があるとはいえ、結婚せずにヒロインの前から姿を消すストーリーのこと。女性の側からすれば、世間的にはキズモノにされ、心にもぽっかりと大きな穴があいた状態で終幕を迎える。
男は、そんなヒロインの心を知ってか知らずか、「幸せになれ…」とか呟いて、哀愁漂うテーマソングを歌って幕ー
こんな話のどこがいいんだか、私には、さっぱりわからない。そういう意味で、「壮大なやり逃げ」と書いた。
今回、「Once upon a time in Takarazuka」(=昔話)という角書きが付いたことで、たぶん、それは時代的なものなんだと、ちょっと冷静に分析してみた。
初演・再演は、50年以上前の日本。それは、皆婚時代。生涯未婚率が5%程度だったとか。
誰でも一度は結婚する時代…もちろん、それを支えたのは、かつて日本の結婚の主流と言われた「お見合い」の存在。特に上流階級では、女学校を出たばかりで、お見合い結婚…というのが、既定路線だったらしい。
そんな女性にとっては、「恋愛」なんてドラマや小説や宝塚の中だけの物語。
菊田先生の周囲にいるお金持ちの奥様は、たぶん、“若い娘が激しい恋をして、身も心も捧げて、でも一夜の思い出を残して男は去ってしまう”みたいなお話が、大好物だったんじゃないかしら。もちろん、そのヒロインに自分をこっそり投影して。
でも、これ、一夜の思い出じゃなきゃダメで、男も去ってくれなきゃいけないっていうのが、上流階級の奥様らしい夢で、つまり、激しい恋の果てに結婚してしまうと、今の生活は手に入れられない…というのは、わかっていて、それは手放したくない。でも、一生の思い出になるような、それでいてギリ綺麗な思い出レベルの「激しい恋」、それが一夜だけの関係なのでは![]() …なーんて。庶民にしてみたら、やり逃げとしか見えなくても。
…なーんて。庶民にしてみたら、やり逃げとしか見えなくても。
菊田先生、どこかから、そんな奥様方の需要を知って、「ダルレークの恋」や本作を書き、ヒットさせたんでしょうね。
私はWOWOWで、順みつきさん主演の「霧深きエルベのほとり」を観た時も、麻路さきさん主演の「ダルレークの恋」を観た時も、なんか、感じ悪い…![]() って思ってしまった。それは、昭和の終りから平成の初めという時代のせいかもしれない。
って思ってしまった。それは、昭和の終りから平成の初めという時代のせいかもしれない。
お見合い結婚より恋愛結婚の割合が増え、結婚前に肉体関係を持つことも当たり前になり…でも、だからこそ、「やり逃げ」は、美しい思い出とかでなく、そこかしこに普通に存在し、それゆえに、「男がズルい」話に見えてしまうようになった。
今回、あまり、そんな気持ちを起こさなかったのは、久美子先生の丁寧な潤色・演出ゆえ…もあったし、平成も30年を過ぎて、そもそも男女関係の破局に際して、どっちかが一方的に悪者とかないし…みたいな時代感になったこともあったし、でもやっぱり、本作の角書きである「Once upon a time in Takarazuka」、昔々宝塚では、こんな作品をやってたんですよ…みたいな「枠」の存在が、この作品を逆に生き生きと、蘇らせたのではないか、そんなことを思いながら、貴重な観劇機会を過ごした。
幕開きから、おなじみのテーマ曲がそのままの編曲で登場し、映画のタイトルの様な文字がスクリーンに映し出されると、誰もが、そこに50年以上昔の宝塚を感じる。50年以上昔から宝塚のファンでいらっしゃるお客様も、最近ファンになったお客様も。
また、このテーマ曲歌唱、指揮の佐々田先生が、歌う紅ゆずるの呼吸を感じるようにタクトを振ってくれていて、なんて贅沢な主題歌なんだろう…![]() と、胸が熱くなった。
と、胸が熱くなった。
歌詞もいいよね~![]()
「霧は深くため息のごと 岸辺によせるさざ波は 別れし人の睫毛にも似て」とか、詩人~![]()
ここで幕が上がると、一気に華やかな現代の宝塚風のプロローグとなる。
ここの展開は、昨年、ショーを手掛けただけあって、大階段にスターが現れ歌う⇒次のスターが現れ歌うと、さっき歌っていたスターが踊る…みたいな流れがとても美しく、それでいて、ビア祭りというテーマは、後に続く物語との整合性もあって、単なるショーにはなっていない。
芝居では辛抱役に徹する2番手の礼真琴が、パワフルに歌い、ダイナミックに踊るのも、この場面の見どころだったし、この公演で退団する七海ひろきの華やかさ、明るさが魅力的な場面だった。お芝居もショーも3番手として送り出そうという、スタッフの意気込みを感じる。
物語は、先ほどから書いている通り、「壮大なやり逃げ」ではあるが、そのことで一番傷ついているのが、逃げたカールであり、その背景に上流階級の人々による「差別」と「上から目線」があって、それを、当の恋人であるマルギットからも感じた結果、カールが逃げ出すことが、しっかりと描かれている。この描き方が徹底されていることで、二人の恋が「どっちもどっち」でイーブンなものに感じられる。
そういう部分は、平成31年風だし、でも、衣装やマルギットのキャラクターはすごくクラシカル。
久美子先生の演出力のおかげで、登場人物の全ての人の気持ちが「あーわかるわかる」となって、なかなか、こんな作品はお目にかかれないな…という感想。
もちろん、出演者の熱演も大きかったが、それは別記事でしっかり書きたい。
上田久美子先生…どこまで、ヒットを飛ばすんでしょうね。神か![]()
さて、本作のプログラムには、菊田先生ご自身が過去の公演時に作者言として載せた文章が転載されている。
初演の時の文章には、この作品を思いついたキッカケについて。ハンブルクに旅行中のある朝、某家の令嬢と船員上がりの青年が恋に落ち、親を説き伏せて婚約したという新聞の三面記事を見たそうで。…とすると、この物語、遠い未来のハッピーエンドを想像することもできるのかもしれない。
再演の時の文章は、ちょっと忘れ難い衝撃だったので、引用させていただく。
もう一本の『お~い春風さん』は、新人植田紳爾の快作です。
「この人、うまくなる人だ」
私、ある日、申しました。
この人がのびてくれると、鴨川清作君や横沢秀雄君など、いまや中堅となった人々のあとに続いて、宝塚からいい作家が生まれます。
今から、ちょうど52年前の4月に書かれた文です。
それから7年後に、植田先生は「ベルサイユのばら」で、宝塚を大ブレイクさせるわけですが、菊田先生は、その一年前に亡くなっていました。もし生きていたら、「ほら、言った通りだろう」とおっしゃっていたかもしれません。
(座付脚本・演出家としての植田先生は、「ベルばら」前にも「メナムに赤い花が散る」「我が愛は山の彼方に」「この恋は雲の涯まで」などを発表し、菊田先生も満足されていただろうとは思いますが、「君の名は」でお風呂屋さんを空にしたと言われる菊田先生レベルの活躍…というと、やはり「ベルばら」ですよね。)




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
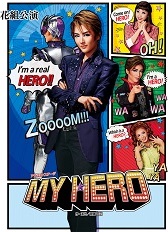


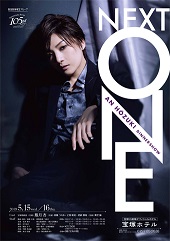




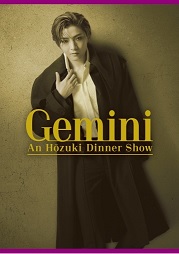
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0