「死と乙女」感想 その7 [┣大空祐飛]
その6はこちらです。
夫、ジェラルドー(豊原功補)の客人、ミランダ氏(風間杜夫)が、かつて自分を拷問した男であると確信したポーリナ(大空祐飛)は、彼を拘束し、真実を告白させようとしている。ミランダに告白を迫ったジェラルドーは、何を告白すればいいかわからないと嘯く彼の為に、告白の内容をポーリナ自身から聞き出そうと、彼女をテラスに連れ出した。
ジェラルドーの捨身の努力によって、ポーリナは過去の体験を語り始めることになった。
レコーダーのスイッチが押された後、促されてポーリナは、自分の名前から話をスタートする。それは、まるで、査問委員会の場に出廷したかのように…。
「私の名前はポーリナ・サラスです。今は、ジェラルドー・エスコバルの妻ですが、当時は独身でした。あの日…1975年4月2日…」
ジェラルドーは、ポーリナの証言に、「もっと詳しく」とか、助言をしながら話を続けさせる。
午後2時15分に通りの角を曲がったところで、ポーリナは、車から降りてきた3人の男にいきなり銃を突きつけられた。その時、彼女を脅した男から、昼食に食べたらしいニンニクの匂いがした。大学でちょうど解剖実習に入っていたポーリナ(彼女は医学生だった)は、ニンニクの匂いを嗅いだ時、ふと、彼の体内で昼食が消化されていく様を想像した。そして、本当なら、「私の名はポーリナ・サラスです。誘拐されかかっています」と大きな声で叫ぶべきだったのに、いとも簡単に誘拐されてしまったのだった。
「これまでの人生で、私はずっと従順すぎたのです」
ここでライトが落ち、彼女のモノローグだけが会場に響く。
ドクター・ミランダに会ったのは、誘拐され、拷問が始まって3日後のことだったと。
彼は、ほかの男たちとは明らかに違い、紳士的だった。彼のかけたシューベルトは、暗闇の中でポーリナを癒した。
舞台が明るくなると、縄を解かれたミランダが、語っている。
音楽をかけたのは、囚人たちからいい人だと思われるし、その方が囚人の苦痛を和らげられると知っていたから。彼は、拷問の中で“いい人”の役割だった。(彼がジェラルドーとポーリナをいい人、悪い人と呼んだのには理由があったんですね!)
彼の兄が秘密警察にいて、今こそ親父の仇を討つ時だと言っていた。
彼らの父は農場主だったが、農民たちの暴動により、土地を奪われ、そのショックで心臓発作を起こして、動くことができなくなった。
「父は、言葉を話すことができなかったが、その目が言っていた。何かをしろ、と。」
ミランダは、とはいえ、本当の本当の本当を言えば、人道的な理由からこの仕事を引き受けたと語る。
本当は嘘だけれども、「これ以上やったら囚人が死ぬぞ」と医師である彼が言えば、拷問は終わる。そうやって、多くの囚人を彼は救った。
けれど、そのうちに、彼の中の悪魔が目を覚ます。
次第に拷問は、彼に快感をもたらすようになっていった。
ポーリナ・サラスが連れてこられた時には、もう、何もかもが遅かった、と彼は述懐する。
風間さんミランダは、椅子を持ってきて、座り、まるでそこにポーリナがいるかのように、覗き込むような姿勢を取る。
「この女は、どれだけの電流に耐えられるのか。ほかの女より強いのか。セックスはどうか。電流を流されたら、彼女のセックスも乾いてしまうのか。こんな状況でも、オーガズムはあるのか」
彼女のすべてが、自分の支配下にある。母親が聞いたら、そんなことはしちゃダメだというようなことが、すべてOK。なんでもあり。
「さあ、ドクター」
一人の男が言う。スタッド、種馬というあだ名の男だった。
「ご馳走が目の前にあって、タダでやれるってのに、逃す手はねえぜ。こいつら、みんな、アレが大好きなんだ」
それでも、と、ミランダは強調する。
「誰一人死んではいません。男も女も」
溶暗から、再び照明が入ると、ミランダは、机の上で書き物をしている。テープのミランダの声が流れ、彼はそれを書き写す作業をしている。
「私の憶えている限り、私は94人の囚人の尋問に関わっています。ポーリナ・サラスを含めて。これが私の証言のすべてです。許しを請いたいと思います」
テープは続く。
この国が調和と平和を取り戻していくに当たり、この告白が、私の心からの謝罪の証となりますように。
私は、残りの人生を深い秘密を抱えたまま、全うしたいと願っています。自らの良心に苛まれることに勝る辛い罰はないのですから。
ミランダはテープの最後まで書き終えると、署名が必要かと尋ねる。
ソファにどっかりと腰をおろしたポーリナは、
「この告白は、すべて自分の意思によるもので、強制されたものではない、と書きなさい」
と言う。
「それは事実じゃない」
「強制されたいの?」
ピストルを弄びながらポーリナは余裕で言い放つ。
ずっと苦しげだったポーリナは、だいぶすっきりとした顔になっている。クールビューティーの面目躍如![]()
ミランダが署名すると、ポーリナは、紙片をまとめ、それからもう一度、カセットテープをひっくり返して再生ボタンを押す。
「私はいつも音楽をかけた…」
ミランダの声が流れてくる。
「ポーリナ、もう、終わったんだよ」
デッキの再生を止め、ジェラルドーが声を掛ける。
「そうね、だいたいのところは」
ポーリナは、窓の近くに移動する。
依然として、真黒い背景ではあるが、そこには、どうやら夜明け前の海が広がっているらしい。
夜の闇を見つめ、ポーリナは詩的な言葉を呟く。
夜明けまで、こうして何時間もここで海を眺めていたような気がする。夜の間に波が置き去りにしていったものの形を描き出して、その姿を眺め、あれは何なのだろう、潮が満ちて海に戻ったら、またどんな形になるのだろう、と考え…そして今…
その言葉には、すべてが終わり、安心したという響きはない。暗い闇の中、波の音だけが聞こえる。
「あなたが理性のある人でよかった。彼が有罪だとわかっても、あなたは彼を殺さないわね」
「あんな男のために、僕の魂を汚そうとは思わないよ」
ポーリナはジェラルドーに、ミランダの車を出してきてほしいと頼む。ジェラルドーは躊躇する。
「大丈夫、私、もう大人でしょ?」
ポーリナは、笑顔を見せる。茶目っ気のある笑顔。
「彼にジャッキを返すのを忘れないでね」
「君も、シューベルトのカセットを返すのを忘れないように。自分のがあるんだからね」
ジェラルドーは、玄関を出ていく。
その時、彼の胸に去来したものは、なんだったろう。
ミランダは告白した。そして、ジェラルドーはその告白により、彼の罪を確信した。
そして、彼の運命をポーリナに委ねたのだ。
もちろん、できれば、妻に犯罪を犯してもらいたくないと思いながら、そうなったらそうなったで、すべてを闇に葬る覚悟をした上で。
清廉潔白な弁護士としての自身の人生に幕を引き、ポーリナの夫として生きることを決めたのだ。
この芝居の中では、ディテールはまったく登場しないが、ポーリナが受けた拷問と恥辱、その告白には、それだけの重みがあったに違いない。15年間、あえてそこから目を背けてきた自身への戒めも込めて、ジェラルドーは覚悟を決めたのではないだろうか。
ジェラルドーが出て行った後、ミランダは、用を足したいと言い立ち上がる。
「動かないで」
ポーリナは銃を構える。
「今日という日を信じられないくらい素晴らしい日にするために、あなたを殺すわ。あなたがいると穢れるのよ」
気持ちよくシューベルトを聴くためには、ミランダがこの世に生きていてはダメだとポーリナは言う。
「ご主人は、あなたを信じて出て行ったのに、裏切るのか」
そして、ミランダは、あの告白は、ジェラルドーと自分が作り上げた嘘の告白だったと言い出す。
確かな証拠が必要、そんな針の頭ほどの疑問も、彼の告白で消えた、とポーリナは鼻で笑う。
頭に銃を突きつけられ、それでも、神様がご存じだとか、言っているミランダ。
「神様なんか持ち出すのはやめなさい。神がいるかどうか、もう少しで分かるという時に」
そして不敵な笑みを浮かべる。
「スタッド」
訝るミランダにポーリナは種明かしをして見せる。
「きっと大きい人なんでしょうね。男臭くて…でも、爪を噛むのよ、あいつ![]() 」
」
その名前もジェラルドーに聞いた、と言うミランダに、勝ち誇ったようにポーリナは教えてやる。
ジェラルドーに言ったのは、“バッド”(蕾)と言う名前だったと。
ジェラルドーが、自分の話をミランダの告白に使うだろうことは予想できたことだった。
「あの人は自分が誰よりも頭がいいと思っているの。そして、いつも誰かを助けなければ、と思っている。彼を責めないわ。だからこそ彼を愛しているんですもの」
ジェラルドーが、言い換えたのでは?と言い張るミランダ。彼が帰ってきたら聞いてみるといい、と。
けれどポーリナは、ほかにも小さな嘘を混ぜておいた。そのほとんどをあなたは訂正した、と有罪を突きつける。
「でも、私があなたを殺すのは、あなたが有罪だからじゃない。あなたが、まったく後悔していないからよ![]() 」
」
ここに至って、彼はまだ、認めていない。
カタチの上では、彼の告白文が整った。これがある限り、ミランダは決してジェラルドー夫婦を告発できない。
けれど、彼自身はまだ、真実の告白も謝罪も行っていないのだ。
「真実を」
ミランダの口癖、ほんとうの、ほんとうの、ほんとう…を、彼はまだ言っていない。
「10秒待つわ」と言って、数え始めるポーリナ。でも、それは全然10秒じゃない。彼女は、途中、何度も止まる。
撃ちたいわけじゃない。殺したいわけじゃない。それなのに、ミランダは、開き直っている。
「どうせ何を言ったって、君は私を殺すんだ…」
と。そして、最後には、
「ああ、ポーリナ、もうやめにしよう。私には子供がある。その子たちは、私に何かあったら、君を探し出して殺すのか?その繰り返しか?もう、終わりにしよう!」
と言い出す。
それを聞くポーリナは、銃を握りながら、絶望的な哀しみを感じているようだった。
「じゃあ、なぜ、いつも、私のような人間が犠牲にならなければいけないの?なぜ、いつも私たちは譲歩しなければならないの?あいつらの中の一人を殺すことで、私たちは何を失うの?何を失うの、私たち…」
絶叫と共に、大きな波音(それは銃声のようにも聞こえる)、そしてスローモーションのようなミランダの姿を残しながら、幕が下りる。
私は最後のポーリナの嘆きを聞きながら、「私たち」というのは、弱きもの、というよりは、ズバリ女性という風に感じながら観ていた。
肉体的な力、という部分では、一般的に女性は男性に敵わない。
その絶対的な優位性を利用して、男たちはこれまで女たちに何をしてきたのか。
チリの独裁政権下の事件を背景にして、これは、男と女の永遠に理解できない戦いの物語にも見える。
でも、そこには、小さな希望の光が見えるような気もする。ジェラルドーとポーリナが互いの間に見出した妥協点の中に。
幕が下りたあと、客席を利用してエピローグが描かれる。
そのエピローグと、全体的な感想、そして出演者については、次の記事で。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)



![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
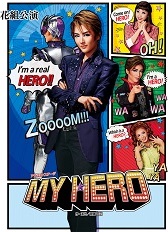


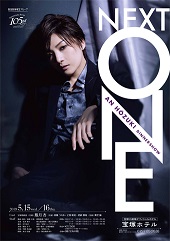




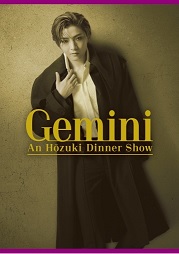
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0