宝塚歌劇星組東京特別公演「赤と黒」観劇 [┣宝塚観劇]
「赤と黒」、人気公演のため、観劇は4月1日の一回だけ。その日に、ケロさんが観劇していて、私はそれを見ただけでドキドキしてしまった。また、幼い日に観劇した初演の影響がことのほか強くて、思い出すことも多かった。
というわけで、かなり注意力散漫な観劇になってしまった。
ミュージカル・ロマン
「赤と黒」-原作 スタンダール-
脚本:柴田侑宏
演出:中村暁
作曲・編曲:吉田優子、(寺田瀧雄)
編曲:河崎恒夫
振付:羽山紀代美、ANJU
装置:大橋泰弘
衣装:任田幾英
照明:勝柴次朗
音響:加門清邦
小道具:福澤和宣
効果:切江勝
歌唱指導:矢部玲司
初演、「恋こそ我が命」というタイトルが、原作の「赤と黒」に改題され、東京で上演されたのは、春3月。
上演した月組は、「ベルサイユのばら」で一世を風靡したメンバーのうち、榛名由梨が花組に異動、初風諄がヨーロッパ公演のため不在となっていた。
トップスターの大滝子は、前年の「ラムール・ア・パリ」辺りから、単独主演になったのかな?当時は、全部の大劇場公演が東上しないので、ほかにも公演があったのかもしれない。まあ、ぶっちゃけ、当時の月組トップは娘役の初風諄だったので、初風のいないこの公演が、大にとっては正念場の公演だったような気がする。
大の演技は、一言で言えば、クサい。
大時代的な芝居をする人だと、子供心に思っていた。そういう芝居は21世紀には流行らないと思う。が、そういう役者がいる時代、脚本家は、その人の演技のリズムに合った七五調のセリフを、知らず書いていたのかもしれない、と、公演を見ながら、思い出していた。
当時、テレビ中継など、ベルばらくらいしかなく、公演実況はLPレコードだった。そんなLPレコードを何度も繰り返し聴いていた。だから、今でも、大滝子のセリフ回しは、耳にこびりついている。
再演の涼風真世主演作品は、一度だけ、有線放送で聴いたことがある。
宝塚作品だけをやっている有線チャンネルが存在していたのだ。で、有線放送を流しているホテルが昔はけっこうあって、遠征の時に聴いた記憶がある。別に作品名を紹介してくれるDJがいるわけではないので、たいてい流されているのが何なのか、わからない。ただ、「赤と黒」は、作品じたいを知っていたので、すぐにわかった。
涼風の演技は、小池修一郎が「人間アニメ演技」と喝破している通り、アニメのような突拍子もないリアクションが妙に似合う男役だった。だから、この「赤と黒」も音声だけだったが、涼風の派手なセリフ回しが自然に受け取れた。
そして、安蘭けい。この「赤と黒」をやりたくて、「おとめ」(宝塚歌劇団が年に一度発行する、生徒名鑑)に書き続けること十余年。ついに念願が叶ったわけだが、安蘭の芝居は、七五調の名調子ではないし、派手なアニメ演技でもない。むしろ、訥々とリアルに心情を訴えるような芝居をする。
なので、どうして安蘭が、「赤と黒」にそこまで固執したのか、私にはよくわからない。
安蘭のような役者が、それほど、カタルシスを感じるような芝居ではない…ような気がするのだ。DSでダイジェストを演じるなら楽しいだろうが、DC公演として真面目に取り組むには、この作品は役不足に思える。今の宝塚において、「赤と黒」はDCではなく、ワークショップ向けの作品なのではないだろうか?
物語はスタンダールの同名小説を下敷きにしている。
舞台は、革命後、ナポレオン時代を経て、王政復古した時代のフランス。
無一文から世界の覇者となったナポレオンを崇拝する、自己顕示欲の強い貧しい青年のエキセントリックな情熱の発露。短い人生の最後に、彼は真実の愛に目覚め、従容として死を受け入れる。
主人公のジュリアン・ソレルは、貧しい生まれだが、それゆえに卑下されることを、非常に嫌う。特に女性に嘲笑われることは、死ぬよりつらいらしい。レナール夫人を誘惑したのも、彼女にバカにされたと思ったのがキッカケだった。
そして、後半、マチルドを誘惑したのも、ジュリアンのプライドが原因。
それが両方とも、婦人のハートをゲットしたのだから、ジュリアンには天性の魅力があったのだろう。
が、レナール夫人の報告によりマチルドとの結婚話は壊れた。怒って、レナール夫人を殺そうとするジュリアン。夫人は死ななかったが、貴族に対する殺人未遂は殺人罪に相当するという刑法の規定を適用してジュリアンは死刑になる。
死に際し、ジュリアンは、レナール夫人への愛に気づき、その限りない愛を抱いて死ねることの喜びを見出す。享年23歳だった。
柴田先生の全盛期の作品。音楽も寺田先生の名曲がそのまま使われている。吉田優子先生の新曲も入っている。23歳で刑死する青年役が似合うかどうかは別にして、とうこさんも大熱演だった。
なんだけど…
よくまあ、こんなにつまらない話になったよなー、と思った。
中村暁演出、恐るべし、である。
この作品は、大劇場作品(1時間30分余)として製作され、その後バウホール作品(2時間余)に作り変えられた。その変更は柴田先生自身がされている。
だから、中村演出にすべての責任を負わせるのは間違っていると思うし、だいたい、演出に中村暁を選んで、変える気がないのは柴田先生自身である。
なのに、つい、中村先生を前面に出して非難してしまうのは、彼の数々の伝説的演出のせいだろうか?
初演時、芝居は法廷から始まった。
裁判長の声、一人スポットを浴びるジュリアン。そこから、物語が回想されていく。
第1場 赤と黒のバラードシーンは、バウホール時点で増やされた場面なのかもしれないが、この場面に緊迫感がまったくないため、第2場 法廷がすっかり死んでしまった。
裁判長の声と、舞台上の被告人の会話から始まる舞台…最近のヅカファンなら、「エリザベート」のパクリ?と思うかもしれないが、初演は、今から30年も昔のこと、こっちの方が古い。堂々とそのままの形を残してくれたら…と思った。
登場人物はそれほど多くない。しかし、裏公演が若手中心のワークショップということもあり、この「赤と黒」には、星組の主だった生徒がほとんど出演している。それほど、見所の多い芝居じゃないのに。
その上、その数少ない登場人物の中で、2番手、柚希礼音が二役をしている。しかも、意味のない二役を。
「赤と黒」の2番手的役どころは、フーケというジュリアンの友人役である。出番は多いとは言えないが、ひたすらジュリアンのことを心配している気のいい友人で、見せ場はいくつも用意されている。ここに柚希が入るのは当然だ。
もうひとつは、コラゾフ公爵。ロシア貴族で、初心なジュリアンに恋の指南をする。
トップと2番手の関係とはいえ、学年は8学年も離れている二人。そこまで学年が離れていると、初めて観た観客でも、どちらが年上かはっきりわかってしまう。なのに、柚希演じる恋愛の大家コラゾフが安蘭演じる若い純情青年ジュリアンに恋愛指南とは…。とてもシリアスな芝居には見えない。
音楽は、初演のものを残し、新曲を追加する形を取っている。
なのに、なぜか、意味不明な詞の変更が行われている。
フーケとの掛け合いの歌、「俺は猟師になる」の部分が、なぜ「俺は狩人になる」と、字余り的変更になったのか、まったく解せない。あの歌は、リズムを刻んで、高揚していく歌なので、“狩人”の語呂の悪さが、尾を引く。盛り上がれない。最低な改変だと思う。
もったいない使われ方をした生徒。
レナール家の下男、サン=ジャン役の水輝涼。歌がないのはもったいない。…でも、水輝が活躍するのは、大野先生作品くらいか…。
神学生のダンサーの中に、美稀千種を発見して驚いた。(もっと早く気づけ!)最後の最後にフリレール副司教という大きな見せ場のある役を演じるのだが、みきちぐが演じるのであれば、第1部から登場するキャラクターに改変してもよかったのに。
ノルベール伯爵の涼紫央、クロワズノワ侯爵の和涼華、ラジュマート男爵の彩海早矢は、まとめて扱われる場面が多く、コラゾフ公爵の柚希礼音と4人で歌い踊る場面など、美男勢ぞろい、という感じだっただけに、もっと活躍の場面があれば…と残念に思う。
本来、この辺りの役どころに使われるべき、若手の二枚目が逆にワークショップに行ってしまっているため、このようなもったいない起用になったと思われる。
ピラール校長の磯野千尋。それほど個性的な役ではないし、組子も役不足なので、わざわざ磯野に出てもらうほどのことはなかったのではないだろうか?
レナール氏の立樹遥。ルイーズ・ド・レナール夫人(遠野あすか)より、かなり年上で、愛のない結婚をして、3人の子供たちを厳格に育てている。二枚目スターの立樹に演じさせる意味がわからない。レナール氏は、年の離れた妻を一人前の人間として扱っていない。自分に従って当然というふうに考えている。だから、ルイーズはジュリアンの若さと無鉄砲さに惹かれたのだが、立樹では、少し年上の包容力のある男性にしか見えないので、ジュリアンに出会う前の、ルイーズの孤独が見えてこなかった。
柴田先生のプログラム寄稿によると、立樹は助演陣の扱いになっている。良くも悪くも華やかな立樹に、このような助演は無理だということが、柴田先生には理解できなくなってしまっているのだろうか。
そんな中、ラ・モール侯爵を演じた萬あきらだけは、実にぴったり配役だったと思う。
私の中では、名優ポジではなく、あくまでダンディなおじさまスタンスだったのだが、最近、芝居に感心することが増えてきた。(除、植田景子作品)今回も、萬のおかげで芝居が締まったように思う。
オープニングの冗長さを書いたが、エンディングも気に入らなかった。
柴田作品では、登場人物の心の中の思いは、テープに録音され、それが流れている間、人物は、テープの音に合った表情をする。この心の声が長くて、けっこう間が持たない出演者がいるのは、毎回お気の毒なのだが、「赤と黒」のラストシーンだけは、ルイーズとマチルドに生の声で思いを語ってほしかった。
独り言になってもいいじゃないか、と思う。
特にルイーズのセリフは、語らせてあげたい。泣きそうになりながら、それを押しとどめて、神様が一日も早く私を召してくださいますよう…と静かに言ってほしかった。
交錯する女たちの声、そして一瞬の閃光とジュリアンの死、ここはラストのカタルシスに向けて、出演者も観客もボルテージを上げていくべき場面。それが、テープの声と、もの言いたげに舞台を横切る演技だけでは、物足りない。
最初と最後の場面を取り上げてみたが、なぜ、「赤と黒」という作品が、安蘭だけでなく多くの男役から支持されてきたか、(大空さんも、演じてみたい役として「おとめ」に書いていた時代があった)それは、この役が演じていて、非常に気持ちいい役だから、だと思う。
ジュリアンは常に挑んでいる。周りのすべてのものに。プライドを守り、それが傷つけられそうになると、獰猛に牙をむく。それらは貴族社会においては、ジュリアンの一人相撲であることが多い。誰も身分の低いジュリアンを傷つけたりバカにしようとはしない。
それなのに滑稽なまでに貴族社会に挑む孤高な姿が、宝塚という世界で、男役を極めようと滑稽なまでの努力をしている男役たちの心を捉えるのではないだろうか。
なので、ジュリアンは滑稽なキャラである。客観的に見ると。
いつもは優しい笑顔を見せてくれるレナール夫人が、ふと手が触れ合った瞬間に手を引っ込めた。夫人はジュリアンを男として意識しているから、手が触れたことにドキッとして手を引っ込めたのだが、ジュリアンはそう受け取らない。
身分の卑しい自分に触れて汚らわしくて手を引っ込めた、と思い込む。そして、その屈辱を晴らすために、時計が10時の鐘を鳴り終わる前に、レナール夫人の手を握り締めようと決意する。その行為は、ジュリアンによれば、ナポレオンの突撃のように勇敢で高潔な行為、ということになる。
マチルドが自分に宛てた恋文の通りに忍んで行こうとしながらも、もし、これが何かの冗談で、マチルドとその取り巻きにからかわれたのだったら、彼ら全員を殺そうと考える。また、からかわれているのなら、行かない方がいいかもしれないと考えながら、そんな敵前逃亡を考える自分を叱咤激励する。
思い込みが激しく、気位が高く、純粋で、自意識過剰な男ゆえに…いや、そんな男が、よみがえった貴族社会に受け入れられなかったゆえの、悲劇。彼の行動のひとつひとつは滑稽だが、その行く先に悲劇が待っていることは、すべての観客が知っている。世界名作とは、そういうものだ。
だから…
ひとつひとつの行動の滑稽さを笑われては、彼の悲劇は、唐突なものになってしまう。
大滝子はエキセントリックなスターだった。涼風真世は人間アニメ演技だった。
それに比べて、安蘭けいは、笑わせてナンボの関西人、サービス精神が旺盛なスターである上に、普段の演技は緻密で繊細、素朴だ。だから、その行動の滑稽さは、彼女のサービスの発露と思われがちであり、笑われる可能性を秘めている。
じゃあ、どうしたら、笑われずにすむのだろうか、と、演出家は考えるべきではなかったのか。
ジュリアンが笑われても、最後には悲劇で終われる自信があったのだろうか?いや、悲劇には見えたのだが、ジュリアンを通して得られるカタルシスはこんなものじゃなかったはずだ、という気持ちが、どうしても抜けなかった。
そして、それは、あの時、笑ってしまったからなんじゃないか…と。
当時の柴田作品が近年立て続けに再演された。初演を知っていると、比べてしまうのは否めないが、それでも、「星影の人」「あかねさす紫の花」は普通に楽しめた。「バレンシアの熱い花」と「赤と黒」には違和感が残った。
そう考えると、出演者の前に、中村暁演出が、どうも私の感性と合わないとしか思えない。
たとえば、謝先生なら、安蘭と「赤と黒」をどう料理しただろうか?と考えずにはいられない公演だった。
出演者の感想は、また別の機会に書きたいと思う。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
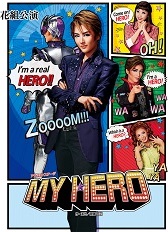


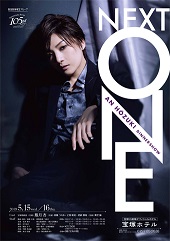




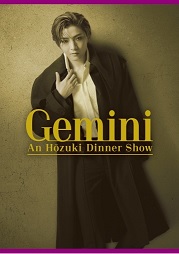
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0