宝塚歌劇雪組東京公演「ドン・カルロス」観劇 [┣宝塚観劇]
グランド・ロマンス
「ドン・カルロス」
~シラー作「スペインの太子 ドン・カルロス」より~
脚本・演出:木村信司
作曲・編曲:長谷川雅大、手島恭子
音楽指揮:寺嶋昌夫
振付:麻咲梨乃
装置:大田創
衣装:有村淳
照明:勝柴次朗
音響:大坪正仁
小道具:松本久尚
歌唱指導:楊淑美
演出助手:樫畑亜依子
舞台進行:阪田健嗣
開演アナウンスで、シラー原作、木村信司脚本、演出(↑)というのを聞いた。
中間にあるヴェルディのオペラはスルーか、と思ったが、実際には、オペラ風に作られた久々の木村歌劇という印象を持った。
本人的には、「君を愛してる」以外は全部木村歌劇なのかもしれないが、私の印象としては、2005年の「炎にくちづけを」以来な感じ。やはり、原作がオペラであるかどうかは、重要なファクターらしい。歌の分量的な問題や、魅力的なアリアがあるかどうか、だけなら、その間に上演された作品群だって十分に木村歌劇と呼べるものだった。
オペラ的世界観(=現実離れしている)があってこそ、木村歌劇は成立するのかもしれない。
舞台は16世紀のスペイン。太陽の沈まぬ王国と呼ばれ、ティリアン・パーシモンが憧れ続けた無敵艦隊を擁するスペイン。
のどかな森で狩りに興じる貴族たち。
ポーザ侯爵(早霧せいな)、フアン(緒月遠麻)、アレハンドロ(彩凪翔)らが、王子ドン・カルロスを探している。
一方、エボリ公女(愛加あゆ)を中心とする淑女たちは、宮廷の男性たちの品定めをしている。主な登場人物の紹介を兼ねていると思うのだが、カルロス王子の次に、しれっとポーザ侯爵の名を出すあたり、エボリ公女、なかなかの役者である。
彼女が隻眼である理由はどこかで触れてほしかったな。
(モデルとなった史実の人物が隻眼だったとはいえ、劇中全く意味がないなら変えるべき。存在が必要以上にクローズアップされて芝居の流れを壊すし、舞台上で片目を隠すのは危険でもある。)
この辺の公女と淑女たちの歌の中で、王子の立場や、周辺の貴族たちのキャラがなんとなくつかめる。王子は変わり者だとか、フアン・デ・アウストリアは実は国王の弟とか。
そして愛する人と結ばれたいと歌う女たちにエボリ公女は聞く。愛を選んで平民になるのですか?と。そう聞かれると、誰も首を縦には振らない。この歌にも当時の貴族達の感性が詰め込まれており、主人公であるカルロス殿下の心情と対比すると、彼の変わり者ぶりがよりわかるようになっている。
そんなところで、事件が起きる。王妃がいなくなったというのだ。
ここで、満を持して主役ドン・カルロス(音月桂)が歌いながら登場する。
音域は高めで、かなり難しそうな楽曲。私が観た時は、喉に負担がかかっているのでは?という歌い方だったが、全体的にはどうだったのだろうか。歌詞を拾っていくと、自分の立場と本当の自分の間で苦しみながらも前向きに生きている青年らしい。
彼の悩みの原因のひとつに父親との不仲がある。
父、国王フェリペ二世(未涼亜希)は、大帝国を継がせる嫡子ドン・カルロスに対して、常に厳しく接している。カルロスは、父から親子の情愛を受けたことがなく、しかも母は彼が生まれるとすぐに亡くなっている。そして彼は、家族問題だけでなく、恋愛問題も抱えているらしい。
そこへ王妃イサベル(沙月愛奈)付女官のレオノール(舞羽美海)が現れ、王妃を連れてくる。カルロスはレオノールと会話をしたかったようだが、王妃はカルロスに二人だけで話したいことがあったらしい。しかし、二言三言言葉を交わしただけで、前場面で登場したそれぞれを探す人々がそこに現れ、二人は話を進めることができなかった。
国王フェリペ二世は、王子カルロスを召したものの、話すことはすべて食い違う。しかも、息子は、愛するものと結ばれない我が身を嘆いている。
ここで一人になったフェリペの周りに登場する疑心暗鬼の幻覚たち(舞咲りん・朝風れい・千風カレン・透真かずき・大澄れい・舞園るり・悠斗イリヤ・愛すみれ)が面白い。
彼らの歌がフェリペの疑惑をしっかりと箇条書きで説明してくれる。
王妃は王子と二人きりで会っていた。
王妃はもともと王子の婚約者だった。政略結婚の対象で会ったこともないとはいえ、絵姿を交換しており、互いに恋心を持っていた可能性は否定できない。
王妃は王子と同年代であり、つまりフェリペとは親子ほども年が違う。
フェリペは既に40代、男としてカルロスに敵う魅力があるとは自分でも思えない。
こうして、疑心暗鬼にかられたフェリペは、王妃と王子の間を探るための密偵を選び始める。
王子の友人たちは、ネーデルラント帰りのポーザ侯爵の話を聞き、王子を巻き込んでネーデルラントの惨状を国王に訴えようと画策している。
ポーザ侯爵は、身の回りの世話をしてくれていたクララ(星乃あんり)という13歳の少女が、父がドイツ語に訳された聖書に手を出した罪で異端審問にかけられた末に死んでしまい、その悲しみのあまり教会の庭で焼身自殺したことから、この国を救いたいと思うようになったらしい。
ちなみに嘘をついているのでなければ、ポーザ侯爵は、熱心なカトリック信者である。
この辺で、木村脚本のいつもの主張が出てきて、落ち着かなくなる。
彼はクララという少女がなぜ死なねばならなかったのか、という“かわいそうな物語”を盾に、観客を騙そうとしている。
しかし、クララの死の原因に、スペインによるネーデルラント迫害問題は直接絡まない。ロイの死因とロナウドほどの関係もない。
「ハプスブルクの宝剣」にも出てきたように、“神の言葉”を綴ったもの(それが聖書であれ、コーランであれ、トーラーであれ)は、不可侵なものである。翻訳という作業も、狭い意味では、神の言葉を勝手に変えること=神への冒涜と取られる可能性もある。
より多くの人に伝わるように手を加えることは、より神の言葉そのものから遠ざかることかもしれない。
だからエリヤーフーも迫害されたし、その感情は、カトリックだからとかユダヤ教だからとかは、関係ない。日本においても、空海と最澄はその問題で仲違いしたようなものだし。
聖書が世界中の言葉に翻訳されている現在から見れば理不尽なことかもしれないが、16世紀のヨーロッパでは、聖書はそういう位置づけだった。そして熱心な信者といえども、聖書の言葉を直接は知らないのが当たり前だった時代だ。
ここに神の言葉が書いてある、と言われてもそれが本当か嘘か、誰にもわからなかった時代、そんな禁書に手を出したら、そりゃ異端審問になるわな。
だって誰にもわからないなら、悪魔の書かもしれないってことでしょ?
(ちなみに、最近あまりに流行りすぎて亜流が増えているからか、ジョセフ・ピラティス氏の言葉は翻訳禁止になったとか聞きました。本物の神だけでなく、業界の神の言葉もまた不可侵性が認められた、ということかもしれません。)
ネーデルラントで新教が増えていることと、クララの父親の異端審問の間には、直接の関係はない。新教が増えたからこそ、クララの父親が彼らの使う聖書を手に入れやすかったという関係はあるにせよ。そして、新教の信者が自分たちの聖書を読むことは問題ないが、カトリックの信者(クララの父親)が新教の聖書を手に取ったら、そりゃ異端審問である。
何度もここで書いていることだが、(ということは、宝塚の脚本家たちはこの事実を混同するロマンチストが多いようだ)目的(もっと聖書を知りたい)は手段(禁書に手を出す)を正当化しないのだ。そのリスクを知った上で投獄されたのであれば、以て瞑すべしということだ。
その上、悲しみのクララは、焼身自殺をしたと。焼身自殺って、抗議行動ですよ![]() 決して、おとなしいだけの娘ではない。父の死は、あなたたちのせいですよ、と教会を相手に命懸けの抗議。でもそれは所詮、父を愛する娘の側の一方的な思い込みで、当時の人々にしてみたら、禁制の書物に手を出して獄死したのを逆恨みしたとしか思えない。
決して、おとなしいだけの娘ではない。父の死は、あなたたちのせいですよ、と教会を相手に命懸けの抗議。でもそれは所詮、父を愛する娘の側の一方的な思い込みで、当時の人々にしてみたら、禁制の書物に手を出して獄死したのを逆恨みしたとしか思えない。
そしてそう思わないポーザ侯爵は、単にクララへの個人的な思い入れが強すぎるだけ。
ネーデルラントへの圧政をやめさせようというテーマであれば、ここはむしろ宗教問題に焦点を当てずに人道問題で攻めた方がいいんじゃないだろうか。
そうできないのは、後半、物語が異端審問に展開するから、かもしれないが、それにしても、木村先生はわざとアンタッチャブルなテーマを選んで、自己主張しては物議をかもそうとしているように思える。夢の世界には、そんなこと必要ないのに…。
そんな木村先生の熱さを知ってか知らずか、カルロスはポーザ侯爵の訴えを退ける。
カルロスの主張は、木村先生より常識的な感じで、内容的に異端審問になりかねないものなのだから、言い出しっぺのポーザ侯爵はともかく、人道的な思いだけで協調しようとする友人たちに、冷静になれ、と言って行動を控えるように告げる。
けれども、自らはポーザにも告げずに、ネーデルラントの問題を父、フェリペ二世に談判しようとする。他人には大人、自分には青いヤツだな、カルロス。
もちろん、政治問題というのは、そんな簡単には動かない。
“もし選べるのなら、寛容で善意の名君と呼ばれたい”
歴代各国の国王は(女王も)みんなそう思っていただろう。でも、実際に玉座に座ってしまえば、その地位は多くのしがらみでガチガチになっていて、国王が自分の意を通せることなど、そんなに多くない。それなのに、人々は、国王ならできると思い、その望みが叶わないと国王を恨むのだ。
まれに国王が意思を通したとしても、いつの間にか、その意思は大きく歪み、ねじ曲げられていく。
愛人を妻に迎えたくて、つまり離婚して再婚したくて、カトリックを離れ、新しい国教を作ってしまったのは、フェリペ二世の岳父、ヘンリー八世だが、その英国国教会が、400年後には国王が離婚した女性と結婚することに大反対して国王を退位に追い込んだ。なんという悲劇!
しかし、そんな辛さを誰にも打ち明けられず、孤独に耐える、それが国王の務めなのだ。
だから、フェリペ二世は思う。息子も父に批判的にばかりなるのではなく、もう少し父の状況を知ってほしいと。
こういうのって、世襲が義務付けられている仕事を持つ父と息子間の永遠のテーマかもしれない。
誤解したままのフェリペ二世が間者に選んだのは、ネーデルラントから帰国したばかりのポーザ侯爵だった。ポーザは、二人の密会の証拠をつかむ任務を引き受ける見返りに、ネーデルラント総督の地位を要求する。
ネーデルラントの幸福のために、親友を売るわけだ。
だって親友は、ネーデルラントの窮状を救おうとはしてくれなかったもん。←誤解
本当に親友か?
ポーザ侯爵は、頭が悪い設定ではなかったと思う。
しかし、王妃と王子の密会の現場をつきとめたい、という王の要請を受け入れるということは、不義の罪で親友が死刑になってもいいということだ。
どこの世界に、他国の窮状を救うために、親友が死刑になることに協力する人がいるだろう?
もし、そんなことは望んでいない、ただ、国王の命令に従う交換条件としてネーデルラント総督を願い出たまでだ、と言うのであれば、ただの阿呆である。
この辺、木村先生は、ポーザのために何の言い訳も用意してやっていない。それが一番残念なことだ。
一方、王妃は、相変わらずドン・カルロスと話がしたいようだった。王妃のためなら、どんなことでも厭わない侍女のレオノールは、深夜、カルロスの館を訪れる。
カルロスは、レオノールに会えて大喜び。二人は幼馴染で、カルロスはレオノールを今でも愛しているのだった。その思いは、レオノールも変わることがなく、二人はお互いの思いを確認し、打ち解けるものの、大人になった二人の間には、身分という大きな壁が立ちはだかっているのだった。
ここで二人が歌う、カルリートとノーラの歌は、とても美しい。
さて、後日―
王妃イサベルのために仮面舞踏会が開催され、イタリア人画家のティツィアーノ(沙央くらま)が招待されている。沙央は、この場面が唯一の見せ場という気の毒な状態。
でも、華やかに、場面を飾っていた。
イタリアで人気の仮面舞踏会の効能について語るティツィアーノ。なるほど!と、『ロミオとジュリエット』を思い出しながら観ていた。
王妃はフランス王家の出身だが、その母親は、メディチ家出身のカトリーヌ・ド・メディシス。というわけで、イタリア生まれのこの文化が王妃のために開催された、という設定になっている。
仮面をつけていることで、一応、「お互いの素性がわからないことになっている」設定を利用し、カルロスは女官、レオノールと踊る。レオノールも身分を忘れ、カルロスのリードに身を委ねる。
そして、カルロスは、王妃と会う算段を彼女に告げるのだった。
ちゃんと、意味ある設定になっているところが、心憎いが、このような心憎い場面がここだけ!というのがとても残念なのだった。
さて、王妃がカルロスに会って話したかった内容は、「国王を愛している」ということだった。
はぁ?
そこ?
あまりの衝撃の結末は、また後日。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)



![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
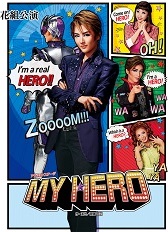


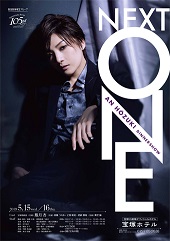




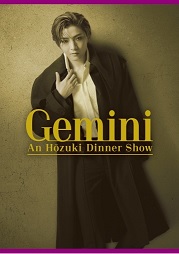
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0