「死の泉」観劇 [┣Studio Life]
「死の泉」
原作:皆川博子
脚本・演出:倉田淳
美術:松野潤
照明:森田三郎、森川敬子
舞台監督:本田和男【ニケステージワークス】、清水浩志
音響:竹下亮、中田摩利子【OFFICE my on】
ヘアメイク:角田和子
衣裳:竹原典子
アクション:渥美博
振付:TAKASHI
映像コーディネート:倉本徹
皆川博子はミステリー作家なので、原作はミステリー仕立てになっている。
ドイツを舞台にし、ドイツ人を主人公に据えた、日本の小説としては珍しい形態だが、それを海外文学の翻訳書として紹介する入れ子構造で書き、ラストの翻訳者による「あとがき」によって、結末がどんでん返しになって、真相が闇に包まれたまま終わる。本自体が一種のトリックになっている代物で、とても面白い。
Studio Lifeの舞台では、翻訳書としての外枠をすべて取り払い、内側の物語のみをドラマ化している。従って、ラストシーンはどんでん返しにはなっていないが、それはそれで、ドラマとして完成されている。
宝塚ファンの方には、『銀ちゃんの恋』がヤスが死ぬところで終わったようなものだと言えばわかるだろうか?(←ちょっとマニアックかな?)
で、その「死の泉」がStudio Lifeで再演された。
初演は、私がファンになる前なので、この公演は、私にとって初めての「死の泉」だった。
ライフの公演では音楽が作品を象徴することが多いが、「死の泉」といえば、「黒い瞳」!もう、果てしなく繰り返されるこの曲が脳裏から離れない。
「黒い瞳」はロシア歌曲だが、タイトルの黒い瞳(オーチ・チョールヌイエ)は、ジプシー(ロマ)の目の色を歌ったものだそうだ。余談だが、ロシア語で、目(瞳)は、グラース(複数形グラザー)で、オーチというのは、古い語彙なんだそうだ。この曲に因んで、五木寛之が黒木瞳の芸名をつけた逸話は有名だが、だから「黒き」という文語調なのかな?と思っている。
今回の公演もWキャストなので、役者については(Reingold/Walkure)の順で記載する。
<ものがたり>
主人公のマルガレーテ(三上俊)は、戦争前に、ギュンター(船戸慎士)という青年と恋愛関係にあったが、ギュンターが白バラのメンバーを当局に密告していたことを知り、別れを告げる。そして未婚のまま、出産するために、レーベンスボルンに入所する。
恋人を軽蔑しつつ、優位な立場で出産をするために、国家的には功労者であるギュンターの名を利用する位のずるさをマルガレーテは持っている。
やがて出産し、生まれたミヒャエルを抱えたマルガレーテに、レーベンスボルンの医師、クラウス(山崎康一/山本芳樹)が求婚する。クラウスは天使の歌声を持つポーランド少年エーリヒ(深山洋貴)と、その兄のような立場の少年フランツ(奥田努)を養子として引き取るため、結婚をする必要が生じたのだった。
こうして、クラウス、マルガレーテ、フランツ、エーリヒ、ミヒャエルという疑似家族が誕生する。
そこに、レーベンスボルンの妊婦だったブリギッテ(吉田隆太)、モニカ(青木隆敏)などが絡みながら、ドイツの情勢が悪化していく様が描かれる。空襲の中、モニカによって暴かれるマルガレーテの秘密と、フランツによるモニカ刺殺事件、そして天使の歌声を残そうとするクラウスによるエーリヒ去勢手術…。
第2部では、いきなり戦後になっている。
クラウスは、ナチスの隠し財産のある古城を買い取ろうと一人の男を訪問するが、彼こそはギュンターであった。成長したミヒャエル(舟見和利/関戸博一)を同道した変わり者の博士に、ギュンターは取り込まれていく。
クラウス家を訪問し、ギュンターはマルガレーテに再会するが、マルガレーテは、明らかに様子がおかしかった。
一方、ブリギッテの生んだクラウスの子供、ゲルト(荒木健太朗)も成長して14歳になっている。彼は、母親から放置されているので、国防スポーツ団のヘルムート(前田一世/仲原裕之)に目を付けられている。
戦争以来行方不明になっていたフランツ(曽世海司/高根研一)とエーリヒ(小野健太郎)はジプシーの歌手になって、義理の父親への復讐の機会を狙っていた。
そんな彼らが、それぞれの目的を達成するため、古城に集う…
<役者感想>
Wキャストではあるが、ポイント的なWなので、役の側面を多面的に表現したい役だけをWにしてみたのかな?と思った。全員が熱演で熱い作品だと思った。
三上俊(マルガレーテ)…圧倒的な美貌でマルガレーテの存在感を示した。また、三上の“熱くない”個性が人形のようなマルガレーテの空虚な美貌にもマッチしていて、まず配役の妙に感心。その上で、三上は主演者として、物語を牽引し得る実力をつけてきたなぁ~としみじみ感動。だって去年はまだ新公に出てたくらいの役者なんだから。
最近は同期の松本を使うことの多い倉田氏だが、ちゃんと三上に相応しい鮮烈なトップ娘役を用意していたんだな、と思うと素直に嬉しい。
今回の役は三上には似合いだったせいもあるが、女性の情緒を理解し始めているように思う。ミナの頃はあちゃーだったからなぁ。
ラストシーンの走りは、それだけで絵になっていた。
山崎康一(クラウス)…原作から抜け出してきたようなクラウス像。最後まで納得できるクラウスだった。しかし、いやな男を演じさせると上手いよなぁ。私はハンサムなきんちゃんが観たいんですけど…。
山本芳樹(クラウス)…クラウスってもしかして、狂人?と原作を読む前にヒントをくれる芳樹クラウス。←褒めてます。山崎クラウスがクラウスという人物の表側を演じ、山本が裏側を演じているような感じで、クラウス像が非常によく掴めた。
芝居の設定では、クラウスが戦前ナチSS将校でありながら、戦後もドイツで普通に暮らしている実情が理解できないのだが、原作を読んで納得すると同時に、山本クラウスにも納得だった。
曽世海司(フランツ/リロ)…義父への複雑な感情を余すところなく表現していて、素晴らしかった。青年になってからは、マルガレーテへの感情が迸る場所がラストシーンしかないのだが、胸が痛くなるような芝居だった。リロは…男にしか見えなかった。
高根研一(フランツ)…ずっと存在感が弱いのだが、ラストで父親を刺す場面からが、超見せ場。すごい迫力で、全場面見せ場の曽世もいいが、このやり方で、フランツの生きた人生がクリアになった部分もあったので、これもWキャストの良さだと思った。
いや、ほんと、ラストは泣けた。三上が飛び込んで抱きついてもビクともしない強靭さも合わせて。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)



![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
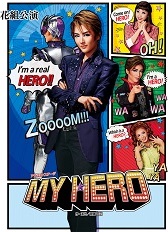


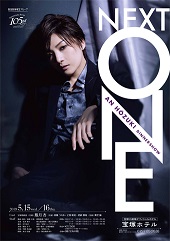




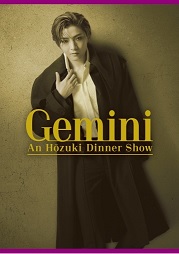
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0