宝塚歌劇月組東京特別公演「グレート・ギャツビー」観劇 その1 [┣宝塚観劇]
ミュージカル
「グレート・ギャツビー」
-F・スコット・フィッツジェラルド作“The Great Gatsby”より-
脚本・演出:小池修一郎
作曲・編曲・歌唱指導:吉崎憲治
作曲・編曲:太田健
編曲:前田繁実、脇田稔
音楽指揮:寺嶋昌夫
振付:尚すみれ、前田清実
装置:大橋泰弘
衣装:有村淳
照明:勝柴次朗
音響:大坪正仁
小道具:市川ふみ、石橋清利
歌唱指導:楊淑美
F・スコット・フィッツジェラルド原作-
この作品ができるまでの背景については、痛いほど調べた。知り過ぎかもしれないと思う。
なので、感想は当然、まっさらな気持でこの舞台だけを見た感想ではない。
ということに、納得していただいた場合は、下の「The Great Gatsby」からお入りください。
最初に、この作品、舞台美術が素晴らしかった、ということを書いておきたい。
幕開き、芝居が始まる前のNYの街並み、ウェストエッグからイーストエッグを臨む「海峡」の景色、そして、小説の描写そのままの「神の眼(エクルバーグ博士の目)」…どれもドラマを大きく盛り上げていたと思う。
舞台は、語り部であるニック・キャラウェイ(遼河はるひ)が、中西部のミネソタ州セントポール(スコットの故郷)から東部のニューヨークに引っ越してきたところから始まる。
彼の新居は、ウェストエッグ7番地。そして隣人、ウェストエッグ1番地から6番地まで使った大邸宅に住んでいるのが、ジェイ・ギャツビーだという。興味の向くままに、ニックは、隣で催されているパーティーに出席してしまう。
しかし、パーティーでは、主人であるギャツビーを知らない人も多く、人を殺したらしいだの、いや大戦の英雄だの、好きなことを言っている。そして招待されていない客までもが、思い思いに楽しんでいた。
ジークフェルト・フォーリーズ(ブロードウェイでショーをやっている一団)の踊り子たち(妃鳳こころ・美夢ひまり・夏月都)がギャツビーの車で現れると、パーティーは最高潮に。
運転手の彩央寿音のかっこうが、ペネロープ(サンダーバード)の運転手みたいで、なんか笑えた。
そんな中、当たり前のように振舞われているアルコール類を見て、ニックは「酒を飲んでいいのか!」と驚く。
直後、警官隊が踏み込んできて、合衆国憲法修正18条違反で全員を逮捕すると言い出す。
すみません![]()
合衆国憲法修正18条は、「酒を飲むな」っていう法律じゃないんですが…![]()
アメリカ合衆国憲法修正第18条は、「合衆国及びその領土内」において、「飲用」の目的で、「酒精飲料」を、「醸造、販売もしくは運搬し、またはその輸入もしくは輸出を行う」ことを禁止するもの。(現在は、修正第21条によって、この修正18条は廃止されている)
「飲酒」は禁止されていないのだ。
禁酒法の施行は1920年。金に余裕のある人々は、その日を前に、アルコールを山のように買いだめした。
「グレート・ギャツビー」は1922年の春から始まる物語なので、ギャツビーが1920年より前に自分で買いだめしておいたお酒を無料で振舞う分には罪にはならない。
もし、警官が踏み込むとすれば、その酒が「密造酒」など不正に売買された証拠を掴んだ場合に限られるし、その場合でも、捕まるのはギャツビーだけで、ヨッパな客を捕まえる権利は踏み込んだ警官にはない。
なんというザル法![]()
つまり、ここでギャツビーが華麗に登場し、飲んだくれて寝ている警視総監を起こすことで、客をホッとさせる、実にしゃれた、かっこいい場面が、実はまったくありえないシーンだったわけ![]()
気づかなきゃよかった…
(ラスパの時に、あの時代で飲んだくれるスコットが不思議で調べたのが原因)
まあね。アラビアのロレンスより100年も前に、アラブの戦士として活躍したトマス・キースを改宗もしないままに刑死させちゃうような、宝塚ですからね。
カサノヴァとポンパドゥール夫人を恋愛させるような小池先生ですからね。
もちろん、フィクションを全く認めないのは、芝居や文学を楽しむ上でもったいないとは思う。
ただ、フィクションを上手に信じさせる工夫をしてほしいとは思う。
これは、私の個人的センスなのだが、「合衆国憲法修正第18条」みたいなものすごくホンモノっぽいセリフで嘘は書かないでほしいな。
とにかく、この芝居では、客が逮捕されそうになって、ギャツビー(瀬奈じゅん)が登場する。
「私がギャツビーですが、なにか」
的に、ニコリともせずに現れる紳士。飲んだくれて眠っている一人の男を起こすと、彼が警視総監だったので、警官たちもどうしようもない。しかも、警官たちを免職にしようとする酔っぱらった総監をなだめ、警官たちに邸の警護をさせることでこの場を収める、大人の対応もかっこいい。
客たちは、ギャツビーの手際に感動する。
こうして、ギャツビーと彼を取り巻く環境にニックが興味を示すところでパーティーは終わる。
もちろん原作とは全然違うオープニングなのだが、華やかで、時代の雰囲気がパッとわかる、引きこまれる導入部だと思う。その後のニックとギャツビーの出会いも、原作とは違うのだが、これも華やかなパーティーの後、そのパーティーを開いていた主人が、静かに対岸を眺めている、という見事な対比になっていて、観客が引き込まれる。
うまい作り方だと感心する。
突堤に立つギャツビーは、一心に対岸を見つめている。
ニックが声をかけると、最初、迷惑そうだったギャツビーも、隣人と知り、積極的に自分の話をする。
原作でも、ここでのギャツビーは明らかに言動が怪しいと書かれているが、真実を語ると言いながら、何かを隠そうとしている雰囲気を、口先だけの早口な台詞回しで、瀬奈はうまく表現していた。
自分の出自を語る場面も、本当はもう少し後なのだが、ギャツビーとニックの会話ばかり何度も繰り返しても面白くないので、ここで一気にやってしまう。
モンテネグロの勲章を持っているというセリフを聞いて、それは架空の国なのかな?なんて初演の頃は思っていた。当時はユーゴスラビアの一部だったが、現在は独立国家(共和国)だ。第一次大戦の頃は一応独立した王国で連合国側だったので、たしかにギャツビーに勲章を与える権利はあった。
向こう側に恋人がいるんですか?と聞かれ、ギャツビーは答える。
「だったと申し上げるべきか、今でもと申し上げるべきか、いや、永遠に、とお答えしましょう」
みたいなセリフを。
ニックは能天気に、「私もあちら側に知り合いがいるんですよ。大学時代の友人でトム・ブキャナンというのですが、ご存知ですか?」と聞く。
ギャツビーは、名前は聞いたことがあると答える。明らかに動揺しながら。
「彼の妻が僕のまたいとこで、デイジーというのですが、掛け値なしに、ケンタッキーとテネシー合わせて一番の美人ですよ」
これを聞いて、ギャツビーは、飛び上がらんばかりに驚く。
ニックは気づかずに去って行くが、劇的な効果として、ニックがちょっと抜けたキャラというか、あまり相手のリアクションに気づかない人物であることが、この場合重要に思える。
遼河のニックは、おおらかな感じがあって、ギャツビーの表情の変化に気づかなくても不思議ではない気がする。
この時点で原作のニックとはかなりキャラが違うのだが、語り部であることが、ニックの身上なので、劇作上は問題ないだろう。
次の場面は、トムの家でのデイジー(城咲あい)と友人、ジョーダン・ベイカー(涼城まりな)の会話から始まる。無駄のない登場人物紹介だ。
デイジーは、サン=サーンスの白鳥のレコードをかけながら、バレエのポーズをしている。本格的なレッスンを始めるというデイジーには、作者であるスコット・フィッツジェラルドの妻、ゼルダが重ね合わされている。もちろん、これは、小池の創作部分。
デイジーというキャラクターは、スコットのその他の作品同様、ゼルダの影響を免れてはいないが、モデルとなった女性は、スコットの憧れの人、ジネヴィラ・キングだったと言われている。手に入らない、高嶺の花。
しかし、これだけでなく、小池は、登場人物のあちこちに、作者であるスコットと妻ゼルダのイメージをプラスしている。
ニックもただの中西部のわりと裕福な家の息子ではなく、ミネソタ州セントポールの出身になっているし、ただの金持ちだったデイジーが判事の娘(ゼルダと同じ)になっているし。2州にまたがる美女という設定も、ゼルダのアラバマ・ジョージア一の美女を彷彿とさせる。
そんなデイジーがどんな娘だったかは、原作ではほとんど語られていない。それをこの脚色で小池はかなり詳細に肉付けしているようだ。
そこへニックが登場してデイジーと再会し、ジョーダンと出会う。
一方、デイジーの夫、トム(青樹泉)にはどうやら愛人がいるらしいことがわかる。
トムは破格の金持ちなのだが、大学時代にフットボールの大スターだったため、30にして、人生の下り坂を歩んでいる男だ。しかし若い時にちやほやされた経験と、金持ちの傲慢さから、そのことに気づくこともできず、悪気なく人を傷つけることができる男だったりする。
デイジーは、物質的には恵まれていても、決して幸せではない。
ここでニックが対岸に住んでいることを聞いたジョーダンとの会話から、デイジーは、そこにジェイ・ギャツビーが住んでいることを初めて知る。
動揺したデイジーは、「白鳥」の曲に合わせて、その思いを歌う。
瀕死の白鳥は、最後に鳴くという、本当に好きな人の名を…
「白鳥は死ぬ前にとっても綺麗な声で鳴くんですって」(byローズ・ラムーア@ハリラバ)
ローズが蘇ったかと思った。これは、大空ファンだけの感想だろうが。
次の場面は、トムの愛人、マートル(憧花ゆりの)と、妹キャサリン(夏月都)などフラッパーの歌と踊り。
これも時代を表す、いい場面。
マートルたちは、映画「コットンクラブ」などでおなじみのフラッパースタイル。
憧花は、瞼をブルーに塗り、眉を大きな弧で描き、美人ではないがコケティッシュな魅力のある女性を体現している。
戦争で若い男がみんな居なくなった時、マートルは仕方なく結婚した。でもその後で、本当に好きな人に出会ってしまった。自分は不幸なんだ、と陽気に歌う。
そのまま背景が現れ、そこが、ウィルソンのガソリン・スタンドとなる。
マートルの夫、ジョージ・ウィルソン(磯野千尋)は、いかにも気の弱そうな風采の上がらない男。マートルとは、10歳位離れている感じかな?マートルの言うがまま、彼女を自由にマンハッタンに行かせているらしい。
そこへ、トムとニックが車で現れる。
初演の時は、実際に1920年代を走ったクラシックカーを舞台に上げていたらしいが、その分、袖から見え隠れするにとどまっていた。今回は、それらしい車を作ったようで、普通に舞台上を走っている。
ウィルソンは、トムの乗っている青い車を買いたいらしい。(自分が整備したら、別の買い手に高く売れると思っているようだ。)
ガソリンスタンドの割には、車に執着しているが、実は、原作ではみすぼらしい整備工場で、自動車売買、ガソリンスタンドもやっているという感じ。
ウィルソンの話には耳も貸さず、カタログを持ってこさせ、その間にマートルの熱いキスを交わすトムは、その行動だけで十分に傍若無人であり、誰が演じても、このイメージは変わらないだろう。
青樹は、傍若無人だけど、憎めないおぼっちゃん風の役作りで、トムを演じている。「ファンシー・ダンス」の時に思ったのだが、ちょっとヘタレ風の青樹が、対憧花では、なぜか押しの強い強引な男を自然に演じることができるような気がする。
こうして、はからずも、デイジー夫妻の現状に深入りしてしまったニックは、ジョーダンからの電話で、デイジーとギャツビーの間にあった過去の出来事を聞かされる。
5年前、デイジーは、ケンタッキー州ルイビルで、第一次世界大戦に参戦する兵士の一人、ジェイ・ギャツビーと恋に落ちた。二人はデートを重ねるが、そのことがデイジーの両親に知られ、ギャツビーは無理やり別れることに同意させられる。
一色瑠加と、専科の梨花ますみが、デイジーの両親を演じている。
一色は、とてもダンディーで優しいパパ。こんなパパだったら、私ならファザコンになってしまいそうだ。梨花は、厳格な古い家庭の夫人という感じ。でも意外に夫婦のバランスはいい。
二人の出会いの場面は初演からあったと思うが、デートに出てくる「王子様と王女様」の歌は新曲のようだ。ここで二人の若々しい恋愛を描くことで、後の悲劇を浮かび上がらせようという意図だと思うが、もともとフィッツジェラルドの原作を一度バラバラな要素に展開して、非常に緻密に再構成しているため、17年経って別の場面を挿入すると、うまく嵌まらないのだな、と思った。
17年前ほどの緻密さで、小池がもう一度再構成したとは、今回は残念ながら思えなかった。
5年前、デイジーは18歳だった。子供のころ、自分は王女様だと思ってたと言っても、まあ可愛いから許してやろうと思うギリギリの年齢だ。
一方、現在32歳位のギャツビーは、5年前なら27歳だ。王子様の歌を歌う27歳の男は、ちょっと頼りない愚かな男か、18歳の娘を騙す気満々の男にしか見えない。(原作にはこんな場面はないが、原作のギャツビーは、実は騙す気満々の男が、逆にデイジーに嵌まって抜け出せなくなった)
年齢差としては、ちょうどステファーノとローズの関係に近いと思うが、あんな風に、年上らしく導くような部分があるのが普通じゃないだろうか?
舞台では、騙す気満々という風には描かれていない。心から愛し合っている二人として描かれる。とすれば、やはり、おバカなギャツビーということなんだろうか?
とはいえ、この時点でギャツビーは既に経歴詐称をしている。見た目ほどピュアでもないわけだ。
こういう場面があるのは、ヅカのお約束という考え方もあるが、こんな歌まで作って水増しするほど必要な場面にも見えない。むしろ、これがあることで、「ギャツビー」から遠ざかる気がしてならない。
小池は、何がしたかったのだろうか?
王子様と王女様という言葉からは、「プリンス・スコットとシンデレラ・ゼルダ」が浮かんでは来るが、あまり、繋がりは感じられないし。
5年前の場面を膨らませようとしたのは、わかるのだが、嬉々として王子様の歌を歌う20代後半の男というのは、どう考えても痛々しいし、そんなものはギャツビーではないと思う。
さて、ギャツビーの経歴を調査した母親によって、惨めに断罪されたギャツビーは、戦争に行くことによってデイジーの前から姿を消す。
デイジーはギャツビーの後を追おうとするが、乳母ヒルダ(妃鳳こころ)が、母に知らせ、結局、阻まれてしまう。若いヒルダが超美人だった。
この時、コートにカメオを付けているのを見て、初演、妹のジュディが、ポツリと「カメオ、もらえないわね」と言い、デイジーが投げつけたシーンが鮮明に蘇った。あれは印象的だったな。
今回のジュディは、羽咲まな。恋人未満の少年エディは紫門ゆりや。二人のデュエットはとても愛らしかった。羽咲のちょっとハスキーな低音が、明るい曲に不思議な風合いを付けていて、嵌まった。紫門は、甘くて柔らかい声。少年らしさが自然に出ている。
羽咲は、美人の姉を持った平凡な妹の、自慢したい反面、どこかで姉の不幸を望んでいるような、ちょっと屈折したキャラクターが、なかなか的確だったな、と思う。
ギャツビーを失ったデイジーは泣き叫ぶ。
ばかな子になってやる、と。ここで、新曲「女の子はバカな方がいい」が入るのだが、これも蛇足、というか、この場面に入ると変な感じだ。
だいたい小池は何を以て「バカ」と言っているのだろうか?
愛を閉じ込め、何も考えないようにすることを「バカ」というのだろうか?
むしろ、
Wise men say only fools rush in…
という歌があるように、バカだから恋をするんじゃ?
まあ、小池の主張するように、デイジーがバカな子になって、愛を閉じ込めたとしよう。
で、バカな子になると言いながら手紙は毎日書いたわけ?
たぶん、初演でも、「バカになってやる」と叫んだとは思う。
でもセリフで叫んだだけだから、そんなにインパクトはなかった。
長く歌わせてしまったために、あれ?バカになるってあんだけ歌ったのに、まだ諦めてなかったの?みたいな違和感が生じてしまっていた。
そんなこんなで、場面は、ギャツビーが出資者の一人となっている、もぐり酒場(Speak Easy)、アイスキャッスルへと続く。
アイスキャッスルは、スコットの短編の名作「氷の宮殿」に近い名前だが、あれは、原題が「The Ice Palace」なので少し違う。つまり、このミュージカルは、CastleとPalaceのように、原作とは似て非なる作品という意味なのだろうか?
アイスキャッスルは、酒場なので非合法。したがって、合言葉を知っていないと入れない。
昔見たディズニー映画「ロジャー・ラビット」では、アニメキャラが出てくる秘密クラブへの合言葉が「Walt Sent Me」(ウォルト・ディズニーが私を寄こした)で、すごく洒落てるなと思った記憶があるが、小池なので、「山」「川」だったりする。(この時点では、杜のサヨナラ公演が「忠臣蔵」というのは決まっていないので、ここは単に日本じゃないんだから!みたいなつまらない合言葉である。ちなみに「空」に対しては、「海」ではなくて「雲」らしい)
ここで、ニックは、ギャツビーの友人の一人、相場師のウルフシェイム(越乃リュウ)と知り合う。
全身から胡散臭さを漲らせているこの男を、越乃が怪演している。
ここで、ギャツビーはニックに、デイジーとの再会の場を設定してほしいと頼む。
原作では、ギャツビーがジョーダンに頼み、ジョーダンがニックに頼むというややこしい設定になっているが、それではあまりにも消極的で男らしくないためか、先にニックが事実関係を知っている状態のところで、ギャツビーが頼もうとする、素直な設定になっている。
ギャツビーは単に、なぜ手紙の返事を書かなかったが、という質問に答えるだけだ。
「書かなかったんじゃない、書けなかったんです!」
その激しい調子に、ニックはそれ以上の追及をしない。
と、そこへ、トムが現れ、ニックはギャツビーにトムを紹介する。トムと握手するやいなや、ギャツビーは消えてしまう。トムはその時点で、彼に不快感を抱く。
ここでウルフシェイムとギャングたちの歌と踊り。
というか、ウルフシェイムは相場師で、警察にも顔が利く男という設定だが、原作ではユダヤ人の初老の男で、決してギャングというわけではないし、麻薬の話も小説には登場しない。
が、舞台ではギャングっぽい設定で、麻薬取引もやりたいが、ギャツビーが自分の島ではそれを許さないので手を焼いているという感じ。違法という点では、酒も麻薬も変わらないんだけどな、この時代は。
というか、ギャツビーが守ろうとしているものが、すごく曖昧模糊としているのだ、麻薬に限らず。
そんな風に初演の時には感じなかった小さな綻びが、どんどん広がっていく。
リアルで細かい芸風の瀬奈がギャツビーを演じることで、演劇構成上は緻密だが、細部の綻びには無頓着な小池修一郎の穴が広がってしまったのかもしれない。
ギャツビーの周囲にいるウルフシェイムの息のかかった人物に、ビロクシー(光月るう)とラウル(彩央寿音)がいる。それぞれ初演では、轟悠、香寿たつきが演じた。
この二人は、ハリラバの時には、ステファーノがイタリアから連れてきた二人のスタッフという役どころで出てきたが、私の印象では、彩央の方が目立っていた。
今回は、彩央が大人しく、光月が目立っていたように思う。光月は、目付きの鋭い、意志の強い、ことと次第では悪事に手を染めることも厭わない覚悟を持った男としてビロクシーを作っていたように思う。
デイジーとの再会以降は、またそのうちに。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)


![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
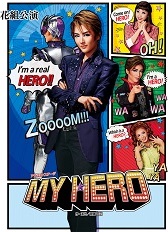


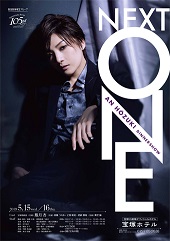




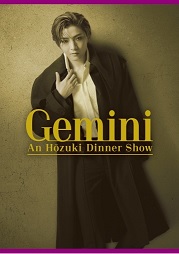
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



修正18条の件、ご指摘ありがとうございます。もう一つ、この作品を台無しにしたセリフはNickのセリフで、Tom Buchananは「Yaleで、フットボールの名フォワードだった」 というセリフです。
アメリカンフットボールにはフォワードというポジションはなく、おそらく、ラグビーと混同しているか、よく解釈すれば、観客に分かりやすくしようとするために原作の「end 」(タイトエンド)を「フォワード」にしたのかもしれません。ただ、このセリフは「彼はサッカーで名ピッチャーだったというようなものであり、少なくともこのセリフを聞いただけで、正直、宝塚にはスポーツをわかる人がいないのだとがっくりきます。特に、関西はアメリカンフットボールが盛んなのに、どうして?という感じです。
僕自身がフットボールをやっていたので、思い入れがあるのかもしれませんが、この作品は全体的に非常によい作品(特に演技者が)だっただけに本当に残念でした。
どこかで、小池氏に指摘したいものです。
by akka (2009-07-10 17:30)
akkaさま
コメントありがとうございます。
フットボールには詳しくないので、そこのセリフは聞き逃してしまいました。
ただ、フィッツジェラルドは、大学時代からフットボールが大好きだったので、その大好きな競技についての描写を間違われたら、きっと悲しむだろうな、と思います。
by 夜野愉美 (2009-07-10 22:29)