「人形の家」観劇感想 その1 [┣大空ゆうひ]
りゅーとぴあプロデュース
「人形の家」
作:ヘンリック・イプセン
訳:楠山雅雄 訳『人形の家』より
上演台本:笹部博司
演出:一色隆司
美術:青木拓也
照明:倉本泰史
音響:清水麻理子
衣裳:坂東智代
ヘアメイク:笹部純
振付:青木尚哉
演出助手:平井由紀
舞台監督:有馬則純
「人形の家」は、そもそもが戯曲になっている。登場人物は6名。舞台が変わらず、幕は時間経過だけを意味する、いわゆる「いっぱい盛り」の作品。
ヒロインのノラ(北乃きい)が、8年前に浅はかな方法で借りた4800クローネが、家族の幸福を脅かすことに…そんなサスペンスの顛末を描きながら、その裏側で、この世界で長年女性たちがどのような存在として扱われてきたか、そのことに女性が気づいた時、男性はどんな目に遭うか…という極めてリアルな人間ドラマが展開する。この作品の衝撃のラストシーンに怯えた男性は、作品発表以来、けっこうな数にのぼるかもしれない。
この作品は、19世紀に書かれたものだが、20世紀には、いわゆる「ウーマン・リブ」運動を扇動する戯曲として紹介されたりしていた。
女性の自立を描いた戯曲と紹介されることが多いので、私も読むまではそんな印象があったが、実際に観劇して思ったのは、現代にも通用するリアルな男女のすれ違い劇だったんだ![]() ということだった。
ということだった。
もっとも、これは、演出家の意図なのかもしれない。
もちろん、ヒロインが、夫に守られて生きてきた家を捨てて出て行くラストシーンは、19世紀に書かれたとは思えないほど衝撃的だし、やはりそこで、思想的な問題を抜きにしてしまっては、本作のテーマを見失ってしまうことも事実だ。
(当時のヨーロッパの上流社会における女性の立場というものから目をそらせば、単なる我儘な奥さんの家出話になってしまい、彼女に同情する観客は居なくなるだろう。そのように上演すること、そして、観ることは、イプセンも許さないはずだ。)
でありながら、思想に特化しない別れのリアルさが、この公演最大の魅力じゃないか、と思った。 夫のトルヴァル・ヘルメルを演じるのは、元光GENJIの佐藤アツヒロ。
元アイドルは今でもイケメン健在。そんな人から、土下座状態で頼まれたら、まあ普通は心が動くはず。でも、夫(パートナー)に心底絶望した人は、相手がどんなにイケメンでも大金持ちでも大統領でも、決して心が戻ることはない。
その前に、心を繋ぎとめるための最後のポイントがあって、そこが決壊したら女性の心は粉々に砕け散っているからだ。
男性でありながら、このメカニズムを知っているイプセンってすごい…![]()
そんな「人形の家」を、今回は、それぞれの登場人物を一人ずつ負いながら、感想を作り上げて行きたい。
カーテンコールの登場順に、まずは、女中のヘレーネ(大浦千佳)。 6名の出演者中、彼女だけがポスターに載っていない。
(ネット上のポスターではもう一人載っていない人がいるのだが、まあそれは、ジャニーズあるあるなので…)
そして、この舞台でカットされた人物は、子供を除いてすべてヘレーネに集約されている。乳母役も、冒頭だけに登場するポーターも。
(ノラがヘレーネに「はい、1クローネ、お釣りはあげる」と言うが、お釣りという言葉に違和感を持った方もいるかもしれない。あれは、原作では荷物を運んでくれたポーターに対して、規定料金+チップをあげた時の台詞なのだ。)
その、ポスターに載らない、集約されてしまう…というところに、この作品を構成する世界線のひとつが見てとれる。
後に、ノラが「パパは大好き、でも女中部屋に忍び込むのも大好き。トルヴァルはパパみたい」と言って、それを聞いたランク博士(渕上泰史)がショックを受けるシーンがある。つまり、この文脈だと、パパ=トルヴァル、女中=自分と聞こえて、彼は不快感を持ったと考えられる。
(現代の日本において、家政婦さんを雇っている…というと、超お金持ちイメージ。家事代行業のようなものを利用されている方はけっこういると思うが、専任の、しかも住み込みの家政婦となると、なかなかお目にかかれない。しかも、原作では、ノラは、自分の乳母を伴ってお嫁に来ているので、実は筋金入りのお嬢様なのだ。)
ノラはあまり気にしていないが、おそらく、この時代、ノラやランク博士のいる世界の下に、ヘレーネたちの生きる世界があったのかな、と想像する。
19世紀ヨーロッパでは、市民として最低限の生活すらできない人々が多く存在し、そういう階層でもお金持ちの使用人という立場なら、衣食住に困らない…みたいな話を読んだ記憶がある。 産業革命の進んだ社会ほど、貧困層の暮らしがひどかったようなので、北欧ののんびりした社会では、イギリスやフランスほどの格差社会ではなかったかもしれないが、原作でも、ノラの乳母は、生活が思うようにいかなかったので、自分の産んだ娘を人手に渡して、ノラの乳母に採用された件が出てくるし。
生まれや育ちが違う相手を、差別まではいかなくても、軽んじるというのは、どこの社会でもある。実際、夫のトルヴァルは、ヘレーネに何の配慮もせずに命令をする。
しかし、ノラという女性は、夫に対する言葉も、ランクに対する言葉もヘレーネに対する言葉も同じ響きを持っている。
彼女は、ヘレーネに何か頼むたびに「ありがとう」と言う。そして、友達同士のように会話を楽しむ。二人の関係が主従であるのは、ひとえにヘレーネ側の忖度が徹底しているからだ。 もちろん、ノラはヘレーネを使用人だと認識していないわけではない。席をはずしてほしい時は「ありがとう」と言うことで彼女が引きさがることを知っている。ただ、相手が誰であっても態度を変えない女性なのだ。この美点は、一度疑問を持ち始めた時、ノラが一気に行動したことにも繋がっているように思う。
乳母と女中の二役を一本化したことで、女主人と使用人の関係性がスッキリして、より理解しやすくなったなーと思う。
そんなヘレーネを演じた大浦千佳ちゃん。外ハネのヘアスタイルが可愛らしく、たぶん7歳くらいの長男の口真似するのもラブリー![]() このお芝居の中で、一番性格の良い人なんじゃないかなーと思うヘレーネをその通り真摯に演じてくれた姿が印象的でした。
このお芝居の中で、一番性格の良い人なんじゃないかなーと思うヘレーネをその通り真摯に演じてくれた姿が印象的でした。
家出を決行しようとするノラに、言葉で諫めることは立場上できないから、涙をたたえながら、首を振りイヤイヤをするのも、可愛かったです![]()
続いて、夫婦の隣人にしてよき友人のランク博士(淵上泰史)。
彼は脊髄に重い病を抱えていて、その原因は父親の放蕩だという。彼の病が噂の通りのカリエスだとすれば、細菌感染が原因であり、父親の放蕩や贅沢病ではないと思うのだが、19世紀はそのように思われていたのかな。
そもそも彼は、トラヴァルの友人だったが、現在は夫婦共通の友人であり、心密かにノラを愛している。
ノラはそのことに気づいているが、トラヴァルは気づいていなかったのか。非常に嫉妬深いヘルメルなので、それはあり得ない気がする。ランクの思いが成就することはない、とタカをくくって、彼の愛するノラを自由にできる自分に酔っているのかもしれない![]()
芝居の場面としては出てこないが、夫妻とランク、そして、リンデ夫人(大空ゆうひ)の4人で食事をした時、ランクは、リンデ夫人に突っかかっていたらしい。ランクは悟っている。自分がもうすぐこの団欒の場から、一人退場することを。
そして、それが愛ではないにせよ、ノラがランクを大好きだということは疑いのない事実だが、それゆえに、ランクを失ったノラが、即座に後釜になる存在を求めるだろうこと、そして既にその候補として都合よくリンデ夫人が現れたことを、ランクは死にゆく者の悲しみと共に苦々しく思っている。
それで、ノラではなく、リンデ夫人に突っかかる。なんとも、悲しい愛の姿だ。
一方、リンデ夫人の方は、ノラとランクの関係を疑う。秘密の愛人ではないのか。こっそりお金を用立ててもらっているのではないか。ノラが天真爛漫すぎて心配なのだ。
ランクがリンデ夫人を後釜候補として考えるのは、彼女と自分が似ているからなんだろうな、と思う。理由などなく、ノラに魅せられ、無償の愛を捧げ続ける。その上、リンデ夫人は女性だから、もっと自然にそれができる。
やるせない思いがつい出てしまった食事会だったのだろう。
この芝居をサスペンス劇とするなら、ランクは、ヘレーネと同様、そこに参加していない傍観者ではある。
しかし、彼の纏う「死」の雰囲気は、確実にノラを追い詰める。
そして、自分と夫の間にランクが存在しなくなる、という事実に直面して、ノラは初めて、夫のモラハラに気づくのだ。
そういう意味で、こっそり重要な人物、ランク博士。
ポスターでは、貧相な小男という雰囲気で写っていたが、実際の渕上さんは、イケメン。やわらかな声と優しい笑顔で客席を魅了する。
観客として、ちょっともったいないな…と思ったのは、渕上さんとアツヒロさん二人ともが、台詞を文節切りするタイプなので、この二人が一緒の場面(つまりラスト手前の重要なシーン)が、やや冗漫に感じられたことだろうか。
次はクロクスタの番だが、ここはゆうひさんリンデ夫人と併せて書きたいので、ちょっと短いが、感想第1幕はこの辺で。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)




![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
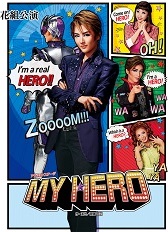


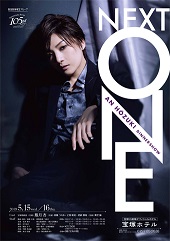




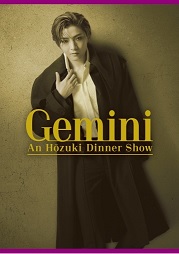
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0