「愛と革命の詩」 その2 [┣宝塚観劇]
全体感想と、蘭寿とむ、蘭乃はなへの感想はこちら。
明日海りお(カルロ・ジェラール)…コワニー家の使用人で平民。父(高翔みず希)もコワニー家の使用人なので、代々仕えているのかもしれない。しかしカルロは、ルソーを愛読し、人間は平等だと信じている。そして、身分違いである令嬢マッダレーナ(蘭乃)に対して、ずっと恋心を抱いている。
フランス革命が勃発すると、カルロはジャコバン党に入り、幹部となる。革命の迷走と粛清の嵐の中、それでもまっすぐ上を向いて生きているカルロ。それは、革命こそ正義であるという信念と、自らの行動に一片の私利私欲もないという矜持ゆえだったのでは?
ところが、ふとしたことから、そのマッダレーナが、ジャコバン党に反旗を翻す組織の人間である、アンドレア・シェニエ(蘭寿)と恋仲であると知り、彼の心に黒いものが宿る。
アンドレア・シェニエへの逮捕状の執行、それはジャコバン党の幹部として当然の行為であるにも関わらず、カルロは平静でいられない。なぜなら彼だけは、その行為が“私情”から出たものであることを知っているからだ。
そして、逮捕されたアンドレア・シェニエを助けてほしいと、愛するマッダレーナが彼の足元に身を投げ出す時がやってくる。しかしカルロは、自分の欲望のままに振舞い、マッダレーナの望まないことを無理強いすることができなかった。彼は、アンドレア・シェニエを呼び出すと、今後、ジャコバン党を擁護する詩を書くと約束するならば、釈放する、と言う。マッダレーナのために。
“私が、それに応じると?”
“いや、あなたは、そんな人ではない”
アンドレア・シェニエの高潔さこそ、カルロの理想であり、そんなカルロの魂もまた高潔なものだったと思う。が、カルロは、高潔な生き方を全うできるほど、裕福ではなかった。ブルジョアであるアンドレアとプロレタリアであるカルロの違い…。
カルロのこの謎かけは、マッダレーナの幸せのために、カルロが思いついた最上の手段だった。本当にジャコバン党を擁護する詩を書かなくても、そう約束するだけで、二人を自由にする。その後、二人が亡命しようとどうしようと知ったことではない。命を懸けてでも、カルロはマッダレーナのために、そこまでの譲歩をしようとした。
でも…高潔な魂の持主である、アンドレア・シェニエが、この謎かけに応じるはずもなく…。
カルロは、アンドレアが愛する女性を前にしても、そんな生き方を選ぶ人ではないのだ、と知り、敗北感に包まれる。その高潔さを前にしては、恥じ入るしかない。
カルロ自身が高潔な魂を内包するがゆえに、この場面は悲しかった。
カルロ・ジェラールという役のポイントは、まさにそこ。彼は決して単なる敵役や悪役ではない。
大劇場で観た時は、その辺がどうも明瞭ではなかったように思ったが、東京に来て、蘭寿のアンドレア・シェニエが高潔そのものになると、明日海のカルロ・ジェラールもまた、人物像がハッキリと見えるようになった。
正直、現在の花組の体制は微妙だと思う。蘭寿が退団を発表しているのに、まだピラミッドのすぐ下に明日海がいるように思えない。
が、今回は、その微妙さが生きた布陣だった。花組の多彩なキャラクターが、総花のように輝くような芝居だったから、その花のひとつとして明日海も見事に輝いていた。
そして、この役を演じ切った明日海の力量に、今後も期待したい。
高翔みず希(老ジェラール)…カルロの父。コワニー家の使用人として分を弁えて仕えている。そして、息子にも自分と同じ人生を歩ませたいと願っていた。
コワニー家が革命で崩壊した後、浮浪者になるが、ジャコバン党幹部となった息子を恥じ、敢えて暴言を吐いて逮捕される。連行は、偶然にもアンドレア・シェニエと同じタイミングで、その時、傷ついたハトがまだ生きていることをユディット(朝月希和)に伝えるシーンがある。ジャコバン党とカルロ・ジェラールに心酔するユディットが、人間的な心を取り戻すキッカケとなる大事な場面だった。
決して自分の生き方を強要するような人物ではなかったし、カルロが革命後の世の中を普通に生きてくれるのなら、それを認めるようなやさしい人物ではあっただろう。しかし、大量虐殺を是とするジャコバン党の幹部が息子であることには、耐えられなかったのだろう。そんな心優しい人物を、高翔らしく、地に足のついた存在感で見せてくれた。
悠真倫(アルフォンス・ルーシェ)…自由主義を信奉するアンドレア・シェニエの同志。地下出版雑誌の編集者。アンドレアのために、通行証を手に入れるなど、献身的に尽くしてくれている。
今回も悠真らしい手堅い舞台だった。
桜一花(ベルシ)…マッダレーナの小間使いだったが、革命下のパリで、マッダレーナを匿う心やさしいムラトーの女性。
いやー、可愛い![]() 世話好きで、心やさしく、恋人の前では超可愛い女。85期の桜が、91期の鳳真由の恋人として普通に存在していることに瞠目した。
世話好きで、心やさしく、恋人の前では超可愛い女。85期の桜が、91期の鳳真由の恋人として普通に存在していることに瞠目した。
華形ひかる(マリー・ジョセフ・シェニエ)…アンドレア・シェニエの弟。詩人、時々脚本家。女優のメルヴェル・ラコット(大河凛)のパトロン兼恋人。高潔な兄を尊敬しながらも、劣等感から一方的に憎悪している。どこまでも高潔な兄に対して、どこまでも人間臭い弟だ。
が、愛する兄が逮捕されるという情報を前に、躊躇せず、危険を伝えに行こうとする。しかし、高潔な兄は、自分だけが助かることをよしとせず…せっかく伝えに来たのに、また否定されてしまった姿が気の毒すぎる…![]()
処刑前の兄に会い、最後の抱擁を受けた時、弟の胸に去来したものは、なんだったのか…。
蘭寿が立っているだけでアンドレア・シェニエだとしたら、華形も立っているだけで、マリー・ジョセフ・シェニエだった。『愛と革命の詩』は、二人の人物を対比することによって、より、クリアに人物像を浮かび上がらせるという手法を繰り返し用いているが、トップスター蘭寿と対比させても遜色なく、人物そのものとして舞台に立っていたと思う。
役者としての華形には、毎度感服するばかりだ。
春風弥里(ジュール・モラン)…モランはカルロ・ジェラールとの対比によって、人物像が浮かび上がる存在だ。
ジェラールにとって、ジャコバン党は、理想を実現するための組織であり、ジェラールの理想は、“平等”というシンプルでポジティブなものだ。一方モランは、革命後の混沌の中で、人々の胸に巣食うどす黒い悪意をエネルギーに変え、“力こそ正義”という状態の恐怖政治を肯定する存在として登場する。
景子先生の作品には、『ジャン・ルイ・ファージョン』にも同様に革命への狂信的な信奉者が登場するが、今回、ロベスピエール役が1シーンしか登場しない&研3の紅羽真希が演じているため、モランの熱さの本質をロベスピエールへの信奉とするには弱い気がする。なので、モランはロベスピエールとは関係なく、恐怖政治を是とする負の存在なのだろう。
春風の熱演と、対比によって役を浮かび上がらせる演出が的確だったことにより、強烈なキャラクターとして印象を残している。
敵役的ポジションではあるが、力強く男らしい人物として、最後のステージを飾ってくれたと思う。
華耀きらり(アリーヌ・ヴァラン)…パンジュ侯爵(望海風斗)の恋人。画家。お腹にパンジュ侯爵の子供を宿していて、その子が25年後、成長して冒頭の場面に母子で登場している。(娘役=春妃うらら)
こんな時代に、平民でありながら、貴族と恋をして、だからこそ、愛や命が本当に貴重なものだということを、誰よりも実感しているのだろう。幸せいっぱいの笑顔の裏側に、芸術家として一人立ちしてきた強さ、母としての強さをも内包し、説得力のある舞台を作った功績は見逃せない。
望海風斗(フランソワ・ド・パンジュ侯爵)…貴族でありながら、人類の平等を信じ、自由主義の信奉者。貴族でありながら、平民の芸術家であるアリーヌを愛し、結婚しようとしている。結果的に、アンドレア・シェニエが使うはずだった通行証によって助かり、25年後に彼の最後の詩を見つけ、出版しようとしている。
芝居の最初と最後にそれから長い年月が経っての物語が入り、そこから回想シーンとして本筋が始まる…という入れ子構造の芝居は、『サン・テグジュペリ』と同じスタイルだが、その時も、入れ子の外側の芝居に出ていた。入れ子を使う作者(演出家)の心理としては、激動の時代をリアルタイムで描くだけでは、主人公がなにものであったか、が描き切れないということだろう。だから、評価が確定する後世に話を持って行って、“彼こそ○○なのです”と結論づけたい。
そして、そういう場に出演する生徒は、その作者の思いを代弁できるだけのゆるぎなさが要求される。
最後の望海の歌唱を見ると、作者が思いを託すに相応しい、舞台の幕を閉じるに相応しい熱があった。
クールで端正な顔立ちに似合わぬ暑苦しさ…花男としての望海は、順調に発酵している。
瀬戸かずや(アベル・ド・フォンダ)、芹香斗亜(シャルル=ルイ・トリデューヌ・ド・モンティニー)ら…アンドレア・シェニエの学友。実在の人物らしい。革命前は、アンドレアが詩人として世に出られるように、手を貸してくれる友人的ポジションだったが、革命後、アンドレアと共に危険な地下運動に身を投じていく。
それだけ、アンドレア・シェニエが魅力的な人物であったのだろう。彼らは貴族だったわけだし。
グループ芝居の域を出てはいないが、それぞれの個性は出ていたと思う。
鳳真由(ファビアン)…ベルシの相思相愛の恋人。マッダレーナ命のベルシが、この男を助けるために、マッダレーナを売る。しょうもない男だけど、惚れた弱み…的なセリフがそれ以前にあって(たしか欠点が200個くらいあるらしい)、それに相応しい情けない男、というキャラクターを見事に表現していた。
高潔な魂を持つアンドレア・シェニエと、その恋人マッダレーナと対比される小市民コンビ。革命は、小市民な彼らの上には、嵐のようなもので、抗うこともできず、打たれるままに通り過ぎるのを待つしかなかったのだろう。そんなことをついつい考えてしまうような、可愛いだめんずのファビアンでした。
冴月瑠那・柚香光(エンジェルズ)…『ロミオとジュリエット』における“愛と死”が、ラストシーンを迎えるまで、常に一定の距離感を持っているのに対して、善と悪を象徴するこの二人は、双子のきょうだいのように分かちがたく結びついているイメージ。その一方で、善なるホワイトは“愛”もつかさどり、悪なるブラックは“死”を呼び寄せる。
大石裕香の振付を一番踊ったのがこの二人だったと思うし、この二人がいないと、せっかくの振付家が生きなかったと思う。また、この二人がいたから、装置の羽根が突飛なものに映らなかったという効果もあった。
『アンドレア・シェニエ』を語る上で本当に必要か?と聞かれると自信はないが、こういう表現方法で作るやり方を否定するまでではないかな。
なにより、二人のダンスの素晴らしさが、二人の存在を肯定していたと思う。
水美舞斗(モーリス・クリヨン)…ルーシェの助手。まだ少年かな?可愛かったです。
彩城レア(アンリ・ド・ラトゥーシュ)、真輝いづみ(ヴィクトル・ユゴー)、航琉ひびき(サント・ブーヴ)…25年後の世界で、アンドレア・シェニエの詩を評価する三人。この三人は、本編でも、さまざまな役を演じ、大活躍だった。
その他、時代を抜け目なく生き抜く居酒屋(なんとLe Paradisという名がついているらしい!)夫婦(天真みちる&仙名彩世)、ちょっとイッちゃった表情が印象的な少女、ユディット(朝月)、10日間、ルイ16世の妹の侍女をしていただけで死刑判決を受けたイデア・ド・レグリエ(乙羽映見)の美声、裁判長を演じた紫峰七海など、多くの生徒が印象に残った。




![★131130_18911_2_R[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/E29885131130_18911_2_R5B15D.jpg)




![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-e49a2.jpg)
![so7q6r0000008bth[3].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/so7q6r0000008bth5B35D.jpg)
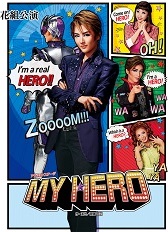


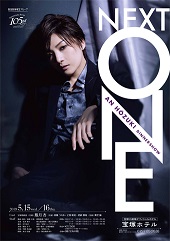




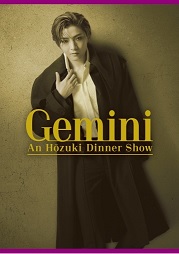
![a01719[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/a017195B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D.jpg)
![revue_img[1].jpg](/_images/blog/_37c/nights-entertainment_troup-leader/revue_img5B15D-c5995.jpg)



コメント 0